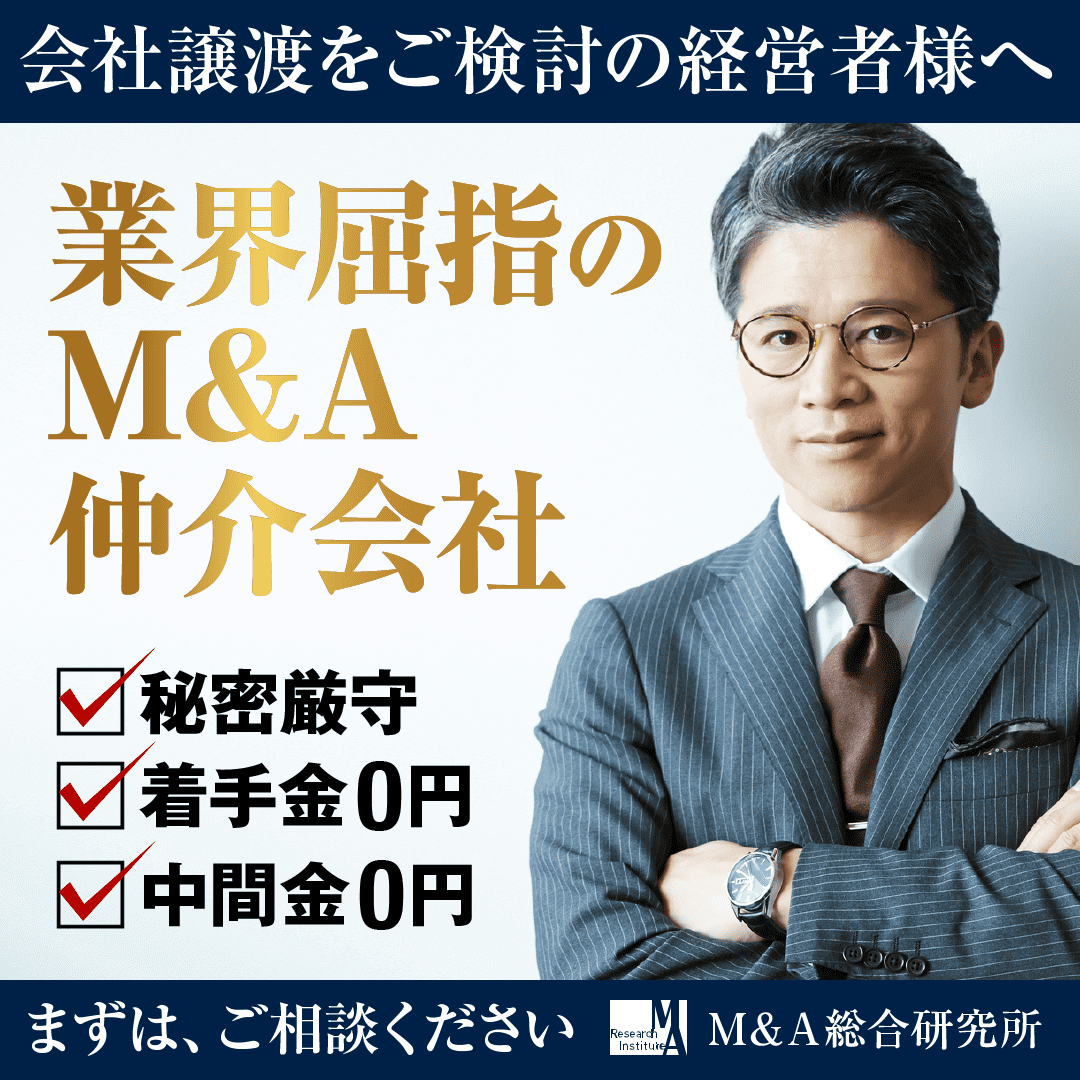2022年09月20日更新
事業承継税制のメリット・デメリットとは?制度内容、注意点も徹底解説
デメリット改善のため平成30年改正が行われた事業承継税制は、中小企業後継者の自社株取得に関し相続税・贈与税を納付猶予する特例です。本記事では、平成30年改正事業承継税制特例の内容とまだ残るデメリット、国税庁や認定支援機関とのかかわりなどを解説します。
目次
1. 事業承継税制とは
まずは、事業承継税制の概要を知りましょう。事業承継税制とは、非上場の中小企業において、現経営者から後継者へ円滑に事業承継が進むのを側面援助する趣旨で制定された制度です。
端的には、中小企業の後継者が新たな経営者となるべく取得した自社株式に関して生じる、相続税・贈与税の納付猶予が受けられるものですが、その詳細について以下に順を追って記します。
定義
事業承継税制とは、非上場の中小企業の後継者が相続税・贈与税について、都道府県知事の認定を受ければ、納税を猶予もしくは免除される特例です。
もともと2008(平成20)年に制定されたものの、2018(平成30)年に大きく法改正が行われています。税制適用の要件が緩和されて、税制適用後のリスクも軽減されました。
事業承継税制を利用すれば、納税の猶予および免除を受けられますが、納税猶予を受けるためには、都道府県知事の認定、税務署への申告手続きが必要です。
なお、事業承継税制の適用を受けられる会社については、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」で定められていますが、詳細は後述します。
目的
事業承継税制が創設された目的は、中小企業の事業承継を促進するためです。近年、中小企業経営者の高齢化が進行しており、帝国データバンクの調査「全国社長年齢分析(2021年)」では、中小企業経営者の平均年齢は60.3歳です。
同じく帝国データバンクの『全国企業「後継者不在率」動向調査(2021年)』によると、後継者不在状況が全体の61.5%で、円滑な事業承継実施が危ぶまれています。
後継者がいないまま、引退年齢を迎えた経営者の選択肢は会社の廃業しかありません。こうした状況が進行すると中小企業は減少してしまい、地域経済へ打撃を与え失業者が増加するでしょう。
そこで政府は、この状況に歯止めをかけるために、税制の面から後継者を支援して事業承継を促進させるべく、2008年に事業承継税制を創設し、国税庁、中小企業庁も協力体制を敷いています。
そして、事業承継税制をより活用しやすい内容に変更した特例が、平成30年改正です。
仕組み
事業承継税制は、相続税や贈与税の納税が猶予もしくは免除される制度です。中小企業の経営者が保有する株式を相続したり、贈与したりすれば、当然、それには相続税や贈与税が課税され、すぐに支払いを行わなければなりません。
しかし、事業承継税制を利用すれば、一定要件のもとで課税の猶予もしくは免除を受けられるのです。
相続のケース
前経営者が、事業承継前に亡くなったケースを相続のケースの事業承継といいます。相続の場合は、相続税がかかりますが、事業相続税制を利用すれば、相続税が猶予または免除されるのです。
生前贈与のケース
前経営者が、存命中に事業承継の準備を進めて、株式を後継者に譲渡するケースを生前贈与のケースの事業承継といいます。生前贈与の場合は、贈与税がかかりますが、事業相続税制を利用すれば、贈与税が猶予または免除されるでしょう。
2. 事業承継税制を利用するための要件
事業承継税制を利用するためには、一定の要件を満たす必要があります。贈与なのか、相続なのかによって要件は異なるので注意が必要です。ここからは、事業承継税制を利用するための要件について詳しく説明します。
特例承継計画の提出
特例承継計画とは、認定支援機関による指導および助言を受けて、会社が作成する経営計画のことです。これまでの事業承継税制では、提出義務がありませんでした。
しかし、平成30年改正の特例では、適用される会社数の拡大にともない、認定支援機関との連携も含めて特例承継計画の提出を求めるようになったのです。認定支援機関との相談のうえ提出する特例承継計画には、主に以下6つの内容を記載します。
- 会社について
- 特例を利用する経営者について
- 特例を受ける後継者について
- 事業承継が行われるまでの経営計画について
- 事業承継後5年間の経営計画について
- 認定支援機関による所見
上記の④については、事業承継を行った後に事業承継税制を利用する場合、記載する必要はありません。⑤の経営計画では、先代経営者と後継者が話し合い、事業の維持・発展のために必要と考えられる事柄について記載します。
売上額など具体的な目標数値は、決まっていなければ記載しなくても問題ありません。いずれにしても、記載内容は認定支援機関とよく相談しましょう。
先代経営者の代表的な要件
平成30年改正の特例において、先代経営者の要件については変更がありませんでした。従来と変わらず、事業承継税制利用における経営者の要件は以下の2つです。
- その会社の代表者であること
- その会社の議決権を半分以上有し、かつその会社における発行済株式総数の過半数以上を有していること
後継者の代表的な要件
後継者の代表的な要件は、次のとおりです。
- 会社の後継者(代表者)であること
- 株式を引き受けた結果、その会社の議決権を半分以上有し、かつその会社における発行済株式総数の過半数以上を有していること
- 20歳以上であること(贈与の場合)
- 役員就任後3年が経過していること(贈与の場合)
認定対象会社の代表的な要件
事業相続税制の規定における、認定対象会社とはならない会社の要件は下記になります。
- 上場会社
- 中小企業者に該当しない会社
- 風俗営業会社
- 資産管理会社(一定の要件を満たすものを除く)
原則、上場していない(株式を公開していない)中小企業であれば、事業相続税制の適用対象となると考えてください。中小企業に該当しない場合は、事業相続税制の適用を受けられません。
風俗営業会社や資産管理会社については、事業相続税制の趣旨と合致しないので、認定対象になりません。
なお、資産管理会社とは、証券、自ら使用していない不動産、現金・預金など特定資産の保有割合が総資産の総額の70%以上の会社(資産保有型会社)や、これらの特定資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社(資産運用型会社)をいいます。
先代経営者以外の株主による贈与について
従来、先代経営者以外の株主から後継者への贈与は事業相続税制の対象とはなりませんでした。平成30年の法改正によって、先代経営者以外の株主による贈与についても事業相続税制の適用対象となりました。
担保提供
相続税もしくは贈与税を猶予する場合は、その額に相当する担保を国税庁に提供することが必要です。ほとんどの場合は、自社株式を担保に提供され、株式については担保株式と呼びます。
株式を発券している会社の場合は、担保株式を法務局へ供託しましょう。株式を発券していない会社は、国税庁・税務署へ必要書類を提出し、担保の提供となります。
5年間の要件
事業承継税制の適用を受けるためには、ここまで紹介してきた要件を5年間守りながら事業を継続しなければなりません。
つまり、事業承継税制を活用したい後継者は、最低でも5年間、経営を維持する気概が必要です。
次の事業承継の要件
5年間事業を継続させた後は、事業承継税制の要件が以下のとおりに緩和されます。
- 対象株式を継続して保有し続けること
- 対象の会社が資産管理会社に変わらないこと
以上の2点を守り続ければ、対象の株式については永久的に相続税が猶予されます。株式を譲渡するなど条件を満たせなくなった場合は、その時点で相続税を支払わなければなりません。
3. 事業承継税制における納税猶予額の計算方法
事業相続税制における納税猶予額の計算は、相続税・贈与税共通で以下の3ステップによって行われます。
贈与時の計算方法
贈与時の納税猶予額は以下のとおり計算を行いましょう。
まず、①贈与を受けた全ての財産における価額の合計額に基づき贈与税を計算します。1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた全財産の価額における合計額を計算しなければなりません。
つぎに、②贈与を受けた財産がこの制度の適用を受ける非上場株式などのみであると仮定して贈与税を計算します。
この制度の適用を受ける非上場株式等にかかる会社などが一定の外国会社などの株式などを有する場合は、その外国会社などの株式などを有していなかったものとして計算した価額です。②の金額が納税が猶予される贈与税となります。
なお、「①の金額」から「納税が猶予される贈与税(② の金額)」を控除した「③の金額(納付税額)」は、贈与税の申告期限までに納付しなければなりません。
相続時の計算方法
相続時の納税猶予額については以下のとおり計算を行うルールです。
まず、後継者の課税価格に対応する相続税を計算します。後継者が取得した全財産の価額の合計額には、不動産・預貯金・非上場株式などが含まれます。外国会社などの株式などは合計額に算入しません。
後継者以外の相続人などが取得した財産の価額の合計と後継者が取得した全ての財産を合計して相続税の計算を行います。
次に、非上場株式に対応する後継者の相続税を計算します。債務や葬式費用がある場合は、非上場株式など以外の財産から先に控除するルールです。これらは相続の際に不可避的に発生するものなので、優先して控除するルールとなっています。
4. 事業承継税制のメリット
ここからは、会社の状態、事業承継の方法など、それぞれのケースにおける事業承継税制のメリットについて見ていきましょう。
どのような企業にメリットがあるのか
事業承継税制の適用がかなえば、中小企業の後継者は相続税・贈与税の納付が猶予してもらえます。
2019年の経済産業省による「中小企業・小規模事業者向け 事業承継の集中支援について」によると、平成30年改正以前は年間約400件程度だった申請が、年間約6,000件の申請に数字が跳ね上がりました。
事業承継税制が平成30年改正の特例でメリットが拡大したことを示しています。そこで、どのような中小企業であれば、そのメリットを享受できるのか、以下に2つの要素を提示するので確認してください。
自社株評価額1億円以上
自社株の評価額が1億円以上の場合、事業承継税制のメリットがあります。自社株評価額が1億円以下であれば、相続税の控除で対応できる可能性があるからです。
相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)と定められています。法定相続人が3人いた場合、基礎控除額は4,800万円です。
また、贈与を行うと相続時精算課税制度を適用でき、1人につき2,500万円まで特別控除されます。3人に相続を行う場合、最大7,500万円分の控除を受けられるのです。
これらの控除を使って、相続税もしくは贈与税の額を軽減できます。しかし、自社株の評価額が1億円以上の場合、これらの控除を用いても納税額がかなりの額になるでしょう。その場合は、相続税・贈与税が猶予される事業承継税制の利用を考えるべきです。
右肩上がり
現在の事業業績が右肩上がりである中小企業も、事業承継税制の利用を考えるべきでしょう。
事業承継税制は、5年間の事業継続ができれば、相続税・贈与税の納付猶予が得られる制度です。事業承継税制を利用し始めてから5年間の業績が右肩上がりになると考えられる場合は、事業承継税制を利用するのが得策です。
親族内承継の場合
親族内承継の場合に事業承継税制を利用すると、後継者に引継ぎしやすいでしょう。事業承継税制で子供や配偶者など身内である後継者への負担を減らせるからです。具体的な負担軽減内容は、以下になります。
- 相続税・贈与税が猶予されるため、すぐに納税する必要がなくなること
- 雇用要件における事実上の撤廃による負担の軽減
- 事業の売却・廃業時に納税額の再計算による差額分の免除
特に平成30年改正により後継者の負担は今までよりかなり軽減されたので、より大きなメリットが得られる状況です。
親族外承継の場合
親族外承継とは、社内の役員や従業員への事業承継です。社内承継ともいいます。この場合、会社を引き継ぐ際には株式取得のために、その対価を支払わないと事業承継できません。そのため、親族外の後継者は莫大な資金が必要です。
対価の支払いは不要で、とにかく社内の人材に事業を引き継いでもらいたいと考える経営者もいるでしょう。
そのような場合、経営者から後継者に株式を贈与することが考えられます。贈与に対して事業承継税制を利用すると、贈与税を100%猶予扱いできます。
事業承継税制を利用するときに限り、親族外承継で相続時精算課税制度が利用可能です。通常、相続時精算課税制度は親族内のみの適用です。しかし、事業承継税制を利用すると、特例として親族外の承継時でも適用を受けられます。
つまり、親族外承継においても、事業承継税制を利用して後継者の税負担を軽減できるのです。
M&Aの場合
M&Aにより事業承継を行う場合は、事業承継税制の適用外です。売却側は、事業を売却して相応の対価として現金収入を得られるメリットがあります。仮に廃業と比較すれば、金銭面では大きなメリットです。
5. 事業承継税制のデメリット
大きなメリットばかりが感じられる事業承継税制ですが、少なからずデメリットもあります。以下、事業承継税制のデメリットについて順を追って確認しましょう。
納税猶予取り消し
事業承継税制が適用されたとき、相続税・贈与税はあくまでも猶予されるだけです。要件を満たし続ければ結果的に免除と同等の状態にはなりますが、表面上は猶予措置なのは変わりありません。
つまり、猶予措置が取り消された場合、相続税・贈与税は即時、国税庁に支払わなければならないデメリットもあります。
取り消し理由
事業承継税制のデメリットとなる適用取り消し条件は、適用開始から5年間までと、5年目以降では異なります。
適用開始5年間の中で事業承継税制の適用が取り消されるのは、適用要件のどれか1つでも満たせなくなったときです。例えば、会社が成長して上場した場合や、後継者が会社の代表者でなくなったケースなどが該当します。
適用開始から5年が経過すれば要件は緩和されますが、一定の条件に達すると相続税・贈与税が猶予されなくなる点は注意が必要です。
具体的には、引き継いだ事業の年間収入がゼロになるケース、資本金・資本準備金が減少するケース、引き継いだ会社が解散・消滅または子会社化されるケースなどが該当します。
上記以外でも、事業承継税制の適用外となる条件・状況があるため、詳細な具体例の確認などは、中小企業庁や国税庁に問い合わせるとよいでしょう。中小企業庁・国税庁ともに、事業承継税制についての説明は、ホームページに記載しています。
特に国税庁のホームページでは、国税庁制作による事業承継税制に関するパンフレットや国税庁の見解がわかるQ&A集、その他事業承継税制の手続き関連など、数多くの資料が閲覧可能です。個人で詳細を調べる際は、一度、国税庁のホームページを見てみましょう。
※参考:事業承継税制(国税庁)
利子税
利子税とは、税金を期限以内に収められなかったとき、本来支払うべき税金とは別に納める必要がある税金です。
事業承継税制の適用中は納税が猶予されますが、その適用が取り消しとなったとき、単に本来の税額を納付するだけでなく、猶予されていた期間分の利子税が課税されます。
当然ながら、利子税は猶予されていた期間が長いほど納税額が多くなる点にも注意が必要です。これもデメリットといえるでしょう。
親族内承継の場合
親族内承継で事業承継税制を利用する場合にもデメリットが存在します。それは、事業承継のために親族内における遺産の分配に偏りが生じ、相続争いに発展する可能性です。
相続争い
事業承継税制を利用するためには、全発行済み株式のうち半分以上を保有する必要があり、経営者はそうなるように後継者に相続させるでしょう。
しかし、親族内で遺産を相続する場合には法定相続分が定義されており、その分を受け取れないときは遺留分を請求できます。そのため、経営者の死後、親族内で相続争いが起こる可能性があるのです。
相続人には遺産をきちんと分配し、かつ後継者には自社株式を引き継げるよう相続対策を行う必要があるでしょう。その対策例として、除外合意や固定合意があります。
除外合意とは、後継者に贈与した自社株式は遺留分の請求ができないと決める合意です。固定合意とは、贈与された自社株式について、遺産分配時の株式価格を贈与時の評価額として計算するように決める合意を意味します。
いずれも自社株が相続争いの原因にならないための対策です。いずれの合意も法定相続人全員の合意が必要となるため、比較的ハードルが高い対策方法といえるでしょう。しかし、デメリット排除のためには、何とかしておくに越したことはありません。
親族外承継の場合
親族外承継の場合、後継者は事業を引き継ぎたい強い意思が必要です。事業承継税制は、引き継いだときの相続税・贈与税の負担を軽減するのが目的です。
後継者が親族外の場合、そもそも後継者にならず、株式の贈与を受けなければ、贈与税を負担する必要はありません。このように感じる後継者候補が多いと、なかなか事業承継は進みません。
事業承継税制は、親族外承継の促進に効果はあります。しかし、永続的に煩雑な手続きが続く事業承継税制の適用を受けてまで後継者になる気持ちのある後継者候補が多くいるかどうか、という点がデメリットになり得ます。
M&Aの場合
M&Aにより事業・会社を売却して事業承継を実現させる場合、事業承継税制の適用を受けられません。つまり、M&Aによる事業承継の場合は、現行の事業承継税制では、その恩恵を受けられないのがデメリットです。
手続きに多くの時間がかかる
事業承継税制を活用するには、煩雑な申請手続きが要ります。都道府県知事への認定申請、税務署での手続き、適用開始後の手続きなどさまざまです。
事業は長く続けることがほとんどなので、納税猶予を受ける期間も長期です。その間に行わなければならない手続きを忘れると、猶予されている贈与税・相続税の全額と利子税を納付する必要があります。
都道府県によって提出書類の種類などが違うことにも気を付けましょう。
対応できる専門家が少ない
事業承継税制は、税理士に依頼することが重要です。しかし、免除にたどり着くまでの過程に、落し穴がたくさんあり、下手をすると損害賠償の請求をされることもあるため、多くの税理士がこの制度に消極的といったデメリットがあります。
税理士には、相続税に強い税理士とそうでない税理士がいるので、相続税に強い税理士を選びましょう。
6. 事業承継税制の注意点
この章では、事業承継税制の注意点について見ていきましょう。
自社株を相続する相続人にのみ恩恵がある
事業承継税制は、自社株を相続する後継者のみ納税猶予を受けられます。それ以外における相続人の相続税は下がりません。この制度を用いても、株式を相続した人のみ恩恵があるので、前もって自社株の株価に対し対策をこうじてから利用しましょう。
各会社に適した株価対策は異なるため、株価評価と個人の資産全体の評価をしてから、総合的な対策を取らなければなりません。遺留分対策も行い、会社、後継者、相続人が円満となる相続にしましょう。
M&Aによる譲渡で贈与税・相続税猶予が打ち切られる
M&Aを実施し、自社株式を第三者に譲渡すると贈与税・相続税猶予が打ち切られます。猶予されていた贈与税や相続税、利子税は、支払わなければなりません。
制度が適用となってから5年過ぎていれば、売却分の株式のみ猶予がなくなります。5年以内であれば、株式の一部譲渡でも猶予が打ち切られるでしょう。
M&Aによる外部売却が増えていますが、事業承継税制は親族内承継を踏まえた制度と考えてください。
7. 事業承継を利用する際の手続き・流れ
事業承継を利用する際は、次の手順で手続きを進めなければなりません。
まずは、特例承継計画を策定します。認定申請会社が作成して、認定経営革新等支援機関が所見を記載したものが必要です。
次に、先代経営者が退任した後、贈与の実行もしくは相続の開始し、都道府県への認定申請を行い、認定証を受領しなければなりません。会社の要件、後継者の要件、先代経営者等の要件を満たしているとして都道府県知事の円滑化法の認定を受けます。
それと同時に、税務署へ納税申告が必要です。申告期限までに、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書および一定の書類を税務署へ提出するとともに、納税が猶予される贈与税額および利子税の額に見合う担保を提供しなければなりません。
ここまでで、事業相続税制の適用は完了となります。
申請認定ののち、申告期限後5年間は、都道府県への年次報告の提出(年1回)が必要です。年次報告を行わない場合は、課税猶予が取り消されます。年次報告書と同時に、税務署へは継続届出書を提出(年1回)しなければなりません。
申告後も引き続きこの制度の適用を受けた非上場株式などを保有するなどにより、納税の猶予が継続されるルールです。ただし、この制度の適用を受けた非上場株式などを譲渡するなど一定の場合(確定事由)には、納税が猶予されている贈与税の全部または一部について利子税と併せて納付する必要 があります。
申告期限から5年経過後には実績報告を行います。実績報告は、雇用が5年平均で8割を下回った場合のみ提出が必要です。6年目以降については、税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)を行います。
8. 事業承継税制における免税・取消事由
事業相続税制は基本的に納税が猶予される制度です。
しかし、後継者の死亡、後継者が次の後継者に贈与税の納税猶予の適用を受ける権利を贈与した場合は、猶予された税金を支払う必要がなくなります。つまり、相続税・贈与税が免除されるのです。しかし、後継者探しは最初からやり直さなければなりません。
また、後継者が代表者でなくなったり、一族の議決権が過半数以下となったり、後継者が一族のなかで筆頭株主でなくなったりした場合は、猶予が取り消されます。せっかく後継者に経営を承継しても、これでは猶予する意味がないからです。これらの取消事由は、事業承継から5年以内に行ったケースに適用されるものです。
5年経過後に、対象となった株式を売却したり、本業を止めたり、3年おきの届出の提出を怠ったりした場合も、猶予の取消しとなる可能性があります。
なお、事業相続税制が開始された当初は、雇用者数を5年平均で8割維持する条件もありましたが、平成30年の制度会社によってこのルールはなくなりました。
9. 事業承継税制におけるセーフティネットの特例
事業相続税制にはセーフティネットが用意されています。
たとえば、経営贈与承継期間の経過後に、民事再生計画の認可決定があった場合など、その時点における非上場株式などの価額に基づき、納税猶予税額の再計算を行い、再計算後の納税猶予税額で納税猶予を継続できる場合があります。その差額は免除されるルールです。
他にも、先代経営者などの死亡などがあった場合は、「免除届出書」「免除申請書」を提出し、その死亡などがあったときに納税が猶予されている贈与税の全部または一部についてその納付が免除されるルールとなっています。
10. 事業承継税制が適用される期間
事業相続税制において、対象となる贈与や相続を行えるのは2018年1月から2028年12月の10年間です。適用期間内に、特例承継計画を策定するなど、一定の手続きを行わなければなりません。
特例承継計画の提出・確認は、2018年から2024年の5年間だけ行えます。したがって、事業相続税制の提供を受けられるのは、実質的に、2024年までです。
11. 個人版事業承継税制について
本記事でここまで取り上げた事業承継税制は、中小企業などの法人を対象としたものです。それとは別立てで、個人事業者向けの事業承継税制が2019年4月1日に創設されています。
両者を区別するため、法人向けについては法人版事業承継税制、個人事業向けは個人版事業承継税制という呼称です。
個人版事業承継税制は、法人版事業承継税制の平成30年改正特例と同様に10年間の時限措置であるため、期限は2029年12月31日までです。
個人版事業承継税制の対象資産
個人事業は法人組織ではないため、株式が存在します。したがって、個人版事業承継税制において贈与税・相続税の猶予対象となるのは、事業主から後継者に贈与・相続される事業用資産です。一般に考えられる事業用資産には、以下があります。
- 土地
- 建物
- 機械
- 器具備品
- 営業用自動車
- その他の固定資産
ただし、事業用資産として認められるのは、貸借対照表に記載・計上されたもの限定です。
個人版事業承継税制の要件
個人版事業承継税制が適用されるための要件は、ほぼ、法人版事業承継税制の平成30年改正特例と同様です。ただし、事業形態の違いにより、個人版事業承継税制独特の要件も含まれる点に注意しましょう。以下に、主な適用要件を掲示します。
- 青色申告を行ってきた事業者
- 後継者も青色申告を継続する
- 2024(令和6)年3月31日までに個人事業承継計画を都道府県知事に提出し認定を受ける
- 個人事業承継計画提出の際は認定支援機関への相談が必要
- 猶予される贈与税に見合う担保を国税庁・税務署に供する
- 後継者は20歳以上
個人事業者からの相続に関しては、別途、「事業用小規模宅地特例」という相続税の特例制度があります。相続人(後継者)は、事業用小規模宅地特例と個人版事業承継税制のどちらかしか活用できない選択制です。選択は専門家に相談し、慎重に判断しましょう。
12. 事業承継税制に関する相談先
事業承継税制を全て理解するのは困難です。また、実際に、事業相続税制の適用を受けようと思ったら、膨大な量の申請書類を用意しなければなりません。
事業承継では、身近に事業承継について相談できる人を見つけることが大切です。
気軽に相談できる商工会・商工会議所はもちろん、高度に専門的な事柄については士業専門家に相談すると良いでしょう。無料で相談にのってくれる機関もあるので積極的に利用してください。
13. 事業承継税制のメリット・デメリットまとめ
事業承継税制の利用を検討するときは、制度の要件、メリットとデメリットをよく理解したうえで判断しましょう。経営者と後継者で意見を交換し、財務に関する専門家や認定支援機関などへ相談したうえで決めてください。
M&A・事業承継のご相談ならM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談なら経験豊富なM&AアドバイザーのいるM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬の料金体系
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期)
- 専門部署による、高いマッチング力
- 強固なコンプライアンス体制
M&A総合研究所は、成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A仲介会社です。
M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。