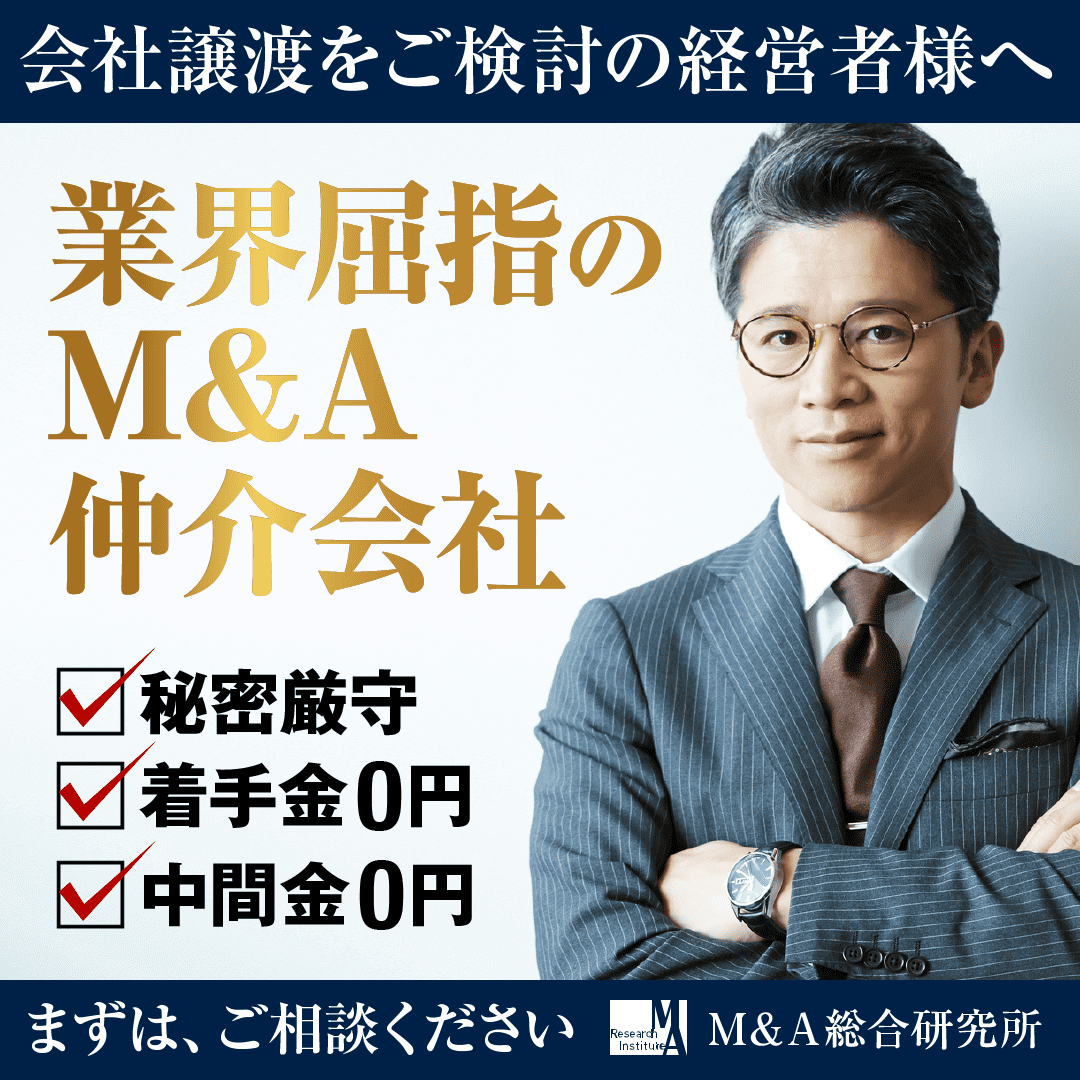2022年12月21日更新
M&Aの税務を解説!税制適格・非適格って何?
M&Aの実施にあたり、税務の問題が発生します。税制適格や非適格などの言葉をよく耳にします。M&Aでは手法により税務の関係が多少違う部分もあるので、ここではそのようなM&Aの税務についてまとめます。M&Aを検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
1. M&Aの税務
M&Aの税務における対象会社の方は、自社にどのような税務の影響があるのか気になるでしょう。
M&Aの税務について対象会社に課税などの影響があるのは組織再編税制によるものです。平成30年度の税制改正が財務省より発表されました。
これにより多くの税目改正が行われています。ここでは、M&Aに関係する税務について詳しくまとめます。
M&Aで発生する主な税金
M&Aで発生する主な税金は、譲渡側の場合、株主のオーナー社長がM&Aで株式を売却したケースや、譲渡企業が退職金を支給したケースで所得税(復興税を含む)と住民税がかかるでしょう。
事業譲渡を用いたケースでは、譲渡企業に法人税などがかかります。消費税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの流通税がかかることもあるでしょう。
譲受側におけるM&Aで発生する主な税金は、退職金や繰越欠損金など、M&Aを行うときだけでなくM&Aを行ってから数年間の譲渡企業における税金計算に影響する事項について税金の検討をしてください。
検討される主な税金について、下記に表を掲載します。
| 取引内容 | 税務取り扱い | 対象となる税金 | |
| 個人株主 | 株式譲渡、不動産売買 | 20.315% | 所得税 復興税 住民税 |
| 個人株主 | 配当 | 最大約50% | 同上 |
| 役員 | 退職金 | 最大28% | 同上 |
| 役員 | 不動産売買 | 20.315% | 同上 |
| 法人株主 | 株式譲渡、不動産売買 | 約34% | 法人税 地方法人税 特別法人事業税 法人事業税 法人住民税 |
| 法人株主 | 配当 | 一定の非課税の措置あり | 同上 |
| 譲渡企業 | 退職金 | 一定金額を損金算入 | 同上 |
| 譲渡企業 | 不動産売買 | 約34% | 同上 |
| 譲渡企業 | 繰越欠損金 | 一定金額を損金算入 | 同上 |
| 譲受企業 | 不動産売買 | 約34% | 同上 |
| 譲受企業 | 配当 | 一定の非課税の措置あり | 同上 |
| 譲受企業 | 投資損失準備金 | 70%以下を損金算入 | 同上 |
M&Aで採用されるスキーム
M&Aで採用されるスキームは、株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併、株式交換・株式移転などです。用いるスキームにより、課税対象が異なる点に気を付けましょう。
M&Aの税務について理解するためには、M&Aがどういった仕組みで行われるのかを理解することも大切です。
組織再編による税務
次に、組織再編と組織再編税制について見ていきましょう。
組織再編とは
組織再編とは、M&Aにて会社組織などの変更を会社法上により行うことです。合併や会社分割、株式譲渡、株式交換、株式移転などがあります。
吸収合併、吸収分割、株式交換など吸収型の組織再編(M&A)と、新設合併と新設分割、株式移転という新しい会社の設立による新設型も組織再編(M&A)に分類できます。
株式譲渡などでのM&Aは組織再編といいますが、他の企業に事業を譲渡するときの事業譲渡によるM&Aや、持ち株会社への変更を行う組織変更は一般的に組織再編とはいいません。
一般的なM&Aで活用される株式譲渡では経営者が変更し、事業ではなく組織の持ち主が変わるため組織再編に当たります。
組織再編税制とは
組織再編税制とは、「合併」「会社分割」「株式譲渡」「現物出資」「現物分配」「株式交換」「株式移転」を含む組織再編行為(M&A)にかかる課税について定めた税制のことです。
株式譲渡などM&Aや組織再編行為をする場合、時価で資産や負債を決めるのが原則であるため、譲渡益に対する法人税やみなし配当課税、株式譲渡益課税が発生します。
ただし、M&Aで資産や負債を移転する場合でも、実質的なその資産や負債に対する支配関係が継続していると認められる際は株式譲渡益を認識されません。
組織再編の際の税制適格・非適格
M&A税務処理関係の組織再編税制には、「税制適格」と「税制不適格」があり、少し複雑な部分もあります。認識ミスによる少しの再編手順の違いで、多額の税金が課せられる場合もあるでしょう。
M&Aにて株式譲渡をする際は、税制適格と非適格を理解しておくと税金対策や税務処理がスムーズに行えます。ここではM&A税務の税制適格・非適格についてまとめます。
税制適格とは
適格組織再編と呼ぶことも多く、組織再編税制で一番重要となるのが「税制適格」です。
税制適格は、M&Aにおける税務処理の税金対策にもつながるので、理解しておきましょう。税制適格とはどのようなものなのか、わかりやすくするために細かく分けて解説します。
定義
M&Aの税務処理で「税制適格」の定義とは、組織自体の統合や分割を主な目的としたM&Aにおける組織再編のことです。
M&Aの会社分割や統合など純粋な組織の分割や合併、統合などの場合に適格組織再編といいます。資産や負債の移転が簿価であり、移転時の課税が繰り延べになるため、課税されず税金対策になるのです。
認められる条件
「税制適格」は、組織再編やM&Aにより資産を移転する前後で実質的に経済に変更がないと認められる簿価の引き継ぎの場合で、課税関係を継続させることが適当だと見なされたときに適用されます。
M&Aにて「税制適格」が認められる条件は以下のとおりです。
- 100%支配関係のあるグループ内での再編・M&A
- 50%越えの支配関係があるグループ内での再編・M&A
- 共同で事業を行っているグループ外企業との再編・M&A
主な条件はこの3つの分類に分けて要件が異なり、分類別の表は以下のとおりです。○の部分を全て満たせば税制適格となります。
税制適格要件①グループ内での組織再編行為
グループ内の組織再編では、金銭などのやりとりがないケース、100%完全支配関係の継続要件、80%以上の従業員の引き継ぎ要件、移転事業の継続要件が対象です。
図を見るとわかるとおり、連結グループ内でのM&Aや組織再編であれば、簡単な要件を達成していれば税制適格と認めてもらえる内容です。
この理由は、連結グループ内であれば組織再編の前後で同じようなビジネスを営むことが見込まれるため、租税回避といった税金対策の心配はなく、組織再編の機動性を確保しても差し支えがないと税務当局が判断しているからです。
税制適格要件②グループ外でもビジネス上の合理性がある組織再編
共同事業などの場合は、グループ内組織再編の要件に加え、事業の関連性や規模、事業参画、株式継続保有など要件をクリアする必要があります。
この要件はグループ外でも租税回避などではなく、ビジネス上の合理性があれば税制適格と判断されるものです。この場合は、税務当局も厳しい目線で見ることが多く、グループ内組織再編より厳しい要件が付いています。
メリット
M&Aにて株式譲渡などの手法により組織再編をした際、税制適格となった場合は合併消滅会社の時価評価が不要になり、消滅会社における青色の欠損金を存続会社に引き継ぐことも可能なので、税金対策になるメリットがあります。
合併存続会社だけでなく組織再編の当事者にもメリットがあるでしょう。消滅会社の株主が存続会社の株式のみを交付されていれば、簿価を引き継いで課税されないため、税金対策としてメリットが大きいです。
税制適格を受けられるM&Aの手法は、税金対策として多くのメリットを獲得できます。
税制非適格とは
次は、非適格組織再編の際に用いられる税制非適格の概要や具体例について見ていきましょう。
基本的に、M&Aなど組織再編行為は税制非適格が原則として定められているため、税制非適格の概要を理解しておくと組織再編税制の理解にもつながります。
定義
M&Aの税務における税制非適格とは、適格要件を満たさない、M&Aの株式譲渡や会社分割、合併、現物出資、株式移転、株式交換などによる組織再編行為のことです。
基本的には税制適格の逆ですが、原則として組織再編行為をする際は「税制非適格」になります。非適格合併や非適格分割ではみなし配当が発生することもあります。
税制非適格は、値するM&Aなどの組織再編行為では、原則どおりに譲渡損益が認識されるため課税対象となるものが多く、税金対策になることは少ないです。
原則税制非適格である理由
税務の原則が税制非適格である理由は、「税制非適格」を基準として、税務上のある一定以上の要件を満たしたときに「税制適格」となるからです。
非適格と聞くと悪いイメージがありますが、あくまでもM&Aの税務上は税制非適格が基準になります。税金対策などの都合でM&Aを行う場合は、税制適格の要件を満たすこともあります。
税制非適格が原則であるのは租税回避を避けるために税務当局が定めたものです。租税回避の具体例を見ていきましょう。
具体例
まずは簡単な例です。
- 簿価150の土地を所有するA会社
- その土地をC会社に時価200で売却
- 税率は40%
次の例は合併した後に資産を売却するケースです。
- A社は簿価150で時価200の土地を保有
- A社とは関係のないB社がA社と合併して資本関係を持ち取り込む(このときA社の企業価値は土地の時価と等価で200)
- B社は繰越欠損金900を持つ
- 合併の後でB社が他のC社にA社から引き継いだ200の土地を売却する
- 税率は40%
これを前提として課税額を考えると、B社が簿価100で土地を引き継ぐと仮定し、B社が合併直後に時価150でこの土地を売れば売却益の50がB社に計上されます。B社は多額の繰越欠損金があるため売却益が消滅する効果があります。
前例ではA社からC社に直接売却すると20の税金が発生するのに対し、この事例では土地の売却で得た売却益が0です。税金対策としてはよいですが、税務当局としてはよくありません。
税務当局はこうした租税回避を避けたいため、合併に関しては原則として合併消滅会社の資産や負債を時価評価にした後で合併する処理規定を設けています。
この税務処理をする合併のことを「非適格合併」といい、M&Aにおける税務の原則的な処理です。
M&A Exitでストックオプションは税制非適格
スタートアップで100%買収によるExitが生じた際、従業員保有のストックオプションは、税制適格要件による譲渡禁止規定があるため、誰かに直接譲渡するのは不可能です。
そのため、従業員は一度権利を行使してスタートアップの株式を購入し、その株式をM&Aを行った企業が購入する手順になります。従業員の取り分は、権利行使価格とM&Aで評価された株価の差額です。
株式譲渡の際の税務
株式譲渡の際、譲渡側の株主が譲受側へ株式を譲渡し、対価として現金などを得ます。譲渡側株主が個人であれば、株式譲渡で得た譲渡所得に所得税が課されます。この所得税は別の所得とは分けて計算する分離課税方式で、税率も一定です。
株主が法人であれば、税金の内訳が異なり、法人税、都道府県民税、地方法人税、事業税、地方法人特別税などが課されます。
株式譲渡による所得・税金
株式などの譲渡で譲渡側が手にするのは、最終合意時に同意した譲渡価額です。そして法人税が課されます。取得費と税金を引いた額が、手元に残ります。
最終的な譲渡所得金額の算出方法は以下のとおりです。
- 譲渡所得金額=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
取得費は、取得金額、設備費、改良費、付随費用を足したものです。
必要な申告
株式譲渡の後、譲渡所得に所得税が課されるので、譲渡の翌年に確定申告と納税を行わなければなりません。
譲渡所得などの額は、「上場株式等に係る譲渡所得などの金額」と「一般株式等に係る譲渡所得などの金額」に分けて税金を計算する申告分離課税です。
申告分離課税は、総合課税を選んだときの配当控除が受けられません。上場株式の譲渡損失があれば損益通算が適応できるので、節税効果が見込めるでしょう。
納税時期
譲渡対価を得た株主は、所得税の確定申告を翌年の3月15日までに実施し、15.315%の所得税をまず納めます。
そして、6月くらいに住所がある自治体から納付書が送付されるので、残り(住民税5%)は納付書が届いてから納税します。
株式譲渡による節税対策
株式譲渡の際は、譲渡側の役員・従業員の退職が考えられるので、譲渡側は譲受側と移転する従業員の雇用条件や制度をすり合わせ退職を防ぎましょう。
それでも役員・従業員が退職する場合は、支払う退職金は会社の損益(経費)として算入できます。退職金を支払った後の残金を株式譲渡の対価として支払えば譲渡側の株式譲渡代金は減り、譲渡側は法人税における節税効果が期待できるのです。
退職金は給与や賞与よりも税金が優遇されるため、譲渡側の創業者における目線において、退職金の活用は節税効果があるといえます。
事業譲渡の際の税務
次に、事業譲渡を行う際の税務について見ていきましょう。
事業譲渡による所得・税金
事業譲渡では、譲渡側の企業が譲受側の企業へ事業の一部または全部を譲渡し、譲渡側が対価として現金などを得ます。課税対象は法人であるため、税金の負担は株主にはありません。
事業譲渡は株式譲渡より税率が高く、譲渡資産によっては(建物・車両運搬具など)一部消費税の課税対象です。
譲受側は、引受ける資産に不動産が含まれると名義変更となり、登録免許税(土地や建物の購入時にその所有権を登記する際に国へ納める税金)や不動産取得税(土地・建物を購入したとき、生前贈与として受取ったときに課税される税金)などの税負担が生じます。
事業譲渡の税務
譲受側が事業譲渡で得た資産の取得価額は、譲渡間際における資産の帳簿価額(簿価)が損金の額に算入されます。譲渡側は、譲渡価額が譲渡手前の帳簿価額より高ければ、帳簿価額を超えた額は譲渡益となり、法人税の課税対象です。
完全支配関係がある法人の間で事業譲渡を行うときは、一定要件を満たせばグループ法人税制が適応となり、譲渡損益が繰り延べられます。設備・店舗など、固定資産を譲渡しているときは、別途消費税の課税があるでしょう。
事業譲渡の納税・節税対策
法人税の納税時期は、2回あります。
- 中間報告分:各事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
- 確定申告分:各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
別途消費税が生じたケースも、原則的に同じ支払時期の設定なので、同時に申告してください。
譲受側の企業は、移動した資産時価以上の部分であるのれん(営業権)に当たる額は、税務上資産調整勘定となり5年間で均等償却し、法人税の算定上損金に参入できるため、のれんが生じると法人税における税金課税対象の利益を5年間減らすことが可能です。
2. M&Aの税負担者と負担額
税制適格や非適格などM&Aの税務に関することをまとめていますが、ここではM&Aを行ったときに税負担者となるのは誰なのか、その負担額はどれくらいになるのかを見ていきます。
M&Aの税務処理を行ううえで非常に重要であるため、税負担についても理解を深めましょう。
税負担者
税負担者は、M&Aの手法やスキームにより対価を受け取る対象が異なるので、どのM&A手法を使うかによってM&A後の手取りは変わります。
税制適格であるかどうかも確認することが必須です。中小企業や中堅企業のM&Aで活用されることの多い「株式譲渡」「事業譲渡」「組織再編」で検討します。
ここでは株式譲渡と事業譲渡のケースに分けて見ていきましょう。
株式譲渡の場合
株式譲渡によるM&Aでは、株主が買収側会社に株式を売却して売却代金を株主が受け取るため、基本的には売却側が税を負担します。
個人の所得は10種類ありますが、この場合は「譲渡所得」として分類され、譲渡益が出たらその分が課税の対象となり、売却側の株主が課税されます。
株主が個人の場合は、株式を売却したことによる譲渡所得として分類されるため、「所得税」としての課税です。税務処理を行うときは、先に譲渡所得を計算します。
事業譲渡の場合
事業譲渡によるM&Aの売却代金は、売却側企業は買収側企業へ事業に関する資産を売却し、対価として代金を売却側企業が受け取ります。
M&Aの売却代金を一定の計算に基づいて計算したときに利益が出ていれば、その売却益が売り手側企業の法人税として会社側に課税されるでしょう。
この場合は、M&Aにおける売却側の株主ではなく、企業そのものが税負担をする形になるのです。
法人の利益に関する税金は、法人税の他に地方法人税、法人住民税、事業税などがあり、これら全てを合わせた理論上の税率を「実行税率」といいます。
負担金額
株式譲渡による税負担金額は、税務処理上、譲渡所得を先に計算しなければなりません。
譲渡所得は、譲渡金額から会社を立ち上げたときの費用や出資金の「取得費」とM&Aにかかった「手数料」を引いて計算します。計算結果の譲渡所得に税率を当てはめて計算するので、所得税15.313%と住民税の一律20.315%をかけて計算します。
例を挙げると、売却金額が10億円の場合、取得費が5%で手数料が3%のときは、所得税が1億4,090万円となり、住民税は4,600万円です。
ただし、住民税は遅れてくるので、それまで納税資金として確保しておく必要があります。
事業譲渡の場合は、譲り渡す事業資産と負債の差額を超えた売却金額が売却益となるためこの部分に課税されます。法人の利益に関する法人税率は実効税率として引き下げの方向にありますが、約30%で概算されるため、売却益の約30%が負担金額です。
消費税の扱い
事業譲渡の場合は、株式譲渡と違い会社に対してかかるため、消費税も課税されます。売却代金から土地代など消費税対象外の資産を差し引いた額に、10%の税率をかけた金額が消費税納税の概算です。
M&Aの売却代金が高いほど課税の対象が大きくなるので、負担も大きくなります。例を挙げると、売却金額が10億円で消費税の非課税分が1億円の場合9,000万円です。
M&Aの途中で株式譲渡から事業譲渡にM&Aの手法を変えたときは課税対象が異なるので、想定していない消費税などがかかり計画が狂うことがあります。税務処理を専門とする税理士に相談し、税金対策などを行いましょう。
のれんの扱い
M&Aの事業譲渡においては、税務上の留意点として「のれん」の扱いに気をつけなければなりません。
事業譲受側の企業は、譲渡の対象事業に関する資産や負債について個別に時価で受け入れ、退職給付債務などに相当する負債を認識します。
そして、事業譲渡の対価と事業に関する時価純資産の差額を資産調整勘定(いわゆる税務上の正の「のれん」)または、税務上の負の「のれん」として差額負債調整勘定を計上し、5年で均等に償却します。
3. M&Aを税理士に依頼するメリット
M&Aを検討したときに、専門的な知識を持つ税理士などに依頼することは必須です。
これまで解説しまとめてきたM&Aにおける税務処理の内容を自身で行うには、かなりの時間がかかり、理解するだけでも容易ではありません。
税理士にM&Aを依頼することでM&A実施の効率化が図れるため、その部分について解説します。
財務状況を細かくチェック
M&Aの税務は、財務状況をしっかりと把握しなければできません。M&Aを行うからと簡単に資料をまとめても、税務に追いつかない場合もあります。
M&Aを税理士に依頼すれば、自身ではわからなかった財務状況まで細かくチェックでき、税理士がいれば対象企業のデューデリジェンス(DD)でも簿外債務などの監査が入念にできます。
M&Aを成功させるには、企業のノウハウや人材も重要ですが、財務状況を税理士にしっかりと見直してもらうことも重要です。税理士にM&Aを依頼することでM&Aによるメリットが大きくなります。
税務に強い
M&Aの税務はスキームにより課税対象が異なることもあり、全てを網羅して把握するのは税理士でなければ難しいでしょう。
また、M&A市場は急成長を遂げている最中で、税務処理関係の改正が毎年度行われていることもあり、年度ごとに税金対策の仕方や、税務処理の方法を変える必要があります。
無茶な税金対策などは法に触れることもあるので、専門の税理士に依頼することが大事です。税理士にM&Aを依頼することで、税金対策に関して安心が得られM&Aでのリスクやトラブルも軽減できます。
数字に基づいた最適な提案
M&Aは多額の取引となるケースが多く、売却金額や譲渡益により、M&A自体がうまくいっても税務処理がうまくいかずに、課税による多額の支出が生じることがあります。そのため、税理士に依頼することは必須です。
税理士に依頼してM&Aを行うことで、M&Aで大事な条件交渉のときなどに、税務処理なども考えて数字に基づいた提案が得られます。税金対策にもつながるので、経営状況の安定化が図れます。
税務処理は基本的に数字に基づくことが大半なので、数字に強い税理士に依頼するメリットは大きいでしょう。
4. クロスボーダー現物出資の適格範囲
平成28年度の税制改正で「円滑で適正な納税のための環境整備」の一項目として、クロスボーダー現物出資の適格範囲の見直しが行われています。
現在ではクロスボーダーM&Aの案件も増えており、M&A後の税負担を軽減させるには、クロスボーダー対象の国外における税制についても理解する必要があります。
クロスボーダーの合併・分割などの組織再編は法的に実現不可能ですが、クロスボーダー現物出資は認められており、適格現物出資要件を満たすことで、世界規模での資産などの簿価移転が可能です。
この税制改正は、クロスボーダー組織再編に伴う課税の弊害是正を目的として行われました。
クロスボーダー現物取引の改正内容とは
クロスボーダー現物出資適格範囲の見直しとして、2016年の税制改正で是正が行われました。
クロスボーダーによるM&A取引は増加しており、国内の税制だけでなく、対象企業国の税制やクロスボーダーに関する税制についても考える必要があります。
ここでは、クロスボーダー現物出資による組織再編の適格範囲など、改正された内容を解説します。
適格の対象に追加されたもの
クロスボーダーにおける適格範囲の改正により追加された項目は、外国法人の恒久的施設に対する国内事業所資産などの現物出資です。
クロスボーダーでM&Aを行う際、外国法人への現物出資でも、国内事業所資産などが国内PEに現物出資される限りは日本で課税機会を喪失することがありません。
そのため、外国法人に対する現物出資のうち、その移転する国内資産など恒久施設に直接帰属するものについては、適格現物出資の対象になりました。
適格対象から除外されたもの
クロスボーダーの組織再編による課税の見直しで、適格範囲から除外されたものは、現物出資1年以内の内部取引により国内PEに移転した資産などの現物出資です。
ただし、内国法人の国内PEが有する資産など外国法人に対する現物出資は、現行制度のもとでは適格対象から除外されていません。
そのため、内国法人が国外PEとの内部取引によって国外事業所資産とした資産をグループ内の外国法人に現物出資した場合、その現物出資は国外事業所資産などの現物出資として適格とされてきました。
改正後は、こうした国外PEを経由した現物出資のうち、現物出資の日の1年以内に内国法人の本店などから内部取引により国外事業所となった資産など、外国法人の国内PE以外における事業所に直接帰属させるものについては、適格対象から除外となりました。
もう一つ、クロスボーダー現物出資の適格対象から除外されたものとして、外国法人による外国法人の国内PEに対する国内外事業所資産などの現物出資があります。
外国法人が国内事業所資産などを内国法人に移転する現物出資は、国内事業所などの含み損が国内に持ち込まれることを防止するために、現行制度においても適格対象から除外されています。
同様に、外国法人が行う現物出資のうち、その移転する国外事業所資産などを他の外国法人における国内PEに直接帰属させるものについては、適格対象から除外となりました。
5. 平成31年の税制改正により追加された項目
平成31年の税制改正によって、追加された項目があります。M&Aに大きく関係する主な項目について見ていきましょう。
三角合併について
以前は、適格合併とされる三角合併の合併対価は、合併法人における完全親会社株式(直接の100%親会社株式)のみでした。しかし、平成31年の税制改正により、間接の100%親会社株式も適格合併とする三角合併の合併対価に含まれます。
逆さ合併について
以前は譲受側が受皿の会社を100%出資で設立し、譲渡企業株式を譲渡で手に入れ、残りの少数株主が保有する株式を株式交換のスクイーズアウトで取得して受皿会社を吸収合併すると、株式交換が他の適格要件を満たしても支配関係継続要件を満たさず非適格株式交換とされました。
そのため、一定資産の評価損益を認識しなければなりませんでした。
しかし、平成31年の税制改正で、他の適格要件を満たし受皿となる会社と譲渡側が合併直前まで支配関係を続けると適格株式交換とされ、評価損益の認識が不要となっています。
受皿会社を存続法人、譲渡企業を消滅法人とする合併であれば適格株式交換とされるので、税務における不整合がなくなります。
6. M&A税務はM&A総合研究所のアドバイザーに!
M&Aを行う際は、税務処理のほかにも多くの手続きが必要です。
M&A総合研究所では、M&Aに精通したM&Aアドバイザーが親身になって案件をフルサポートし、交渉や書類作成、税務処理などを一貫支援いたします。
料金体系は成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」です(※譲渡企業様のみ。譲受企業様は中間金がかかります)。無料相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
7. M&Aの税務まとめ
M&Aなど組織再編税制の税務にかかわることをまとめました。M&Aは現在、国や自治体で促進している活動であるため、税制の改正が行われたり、税務処理に関する取り決めが変更されたりしています。
今回まとめた税制適格・非適格の要件は変更が行われる可能性もあるため、税金対策や税務処理に不安のある方は、税理士などに相談しましょう。
M&A・事業承継のご相談ならM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談なら経験豊富なM&AアドバイザーのいるM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬の料金体系
- 最短43日、平均7.2ヶ月のスピード成約(2025年9月期)
- 専門部署による、高いマッチング力
- 強固なコンプライアンス体制
M&A総合研究所は、成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A仲介会社です。
M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。