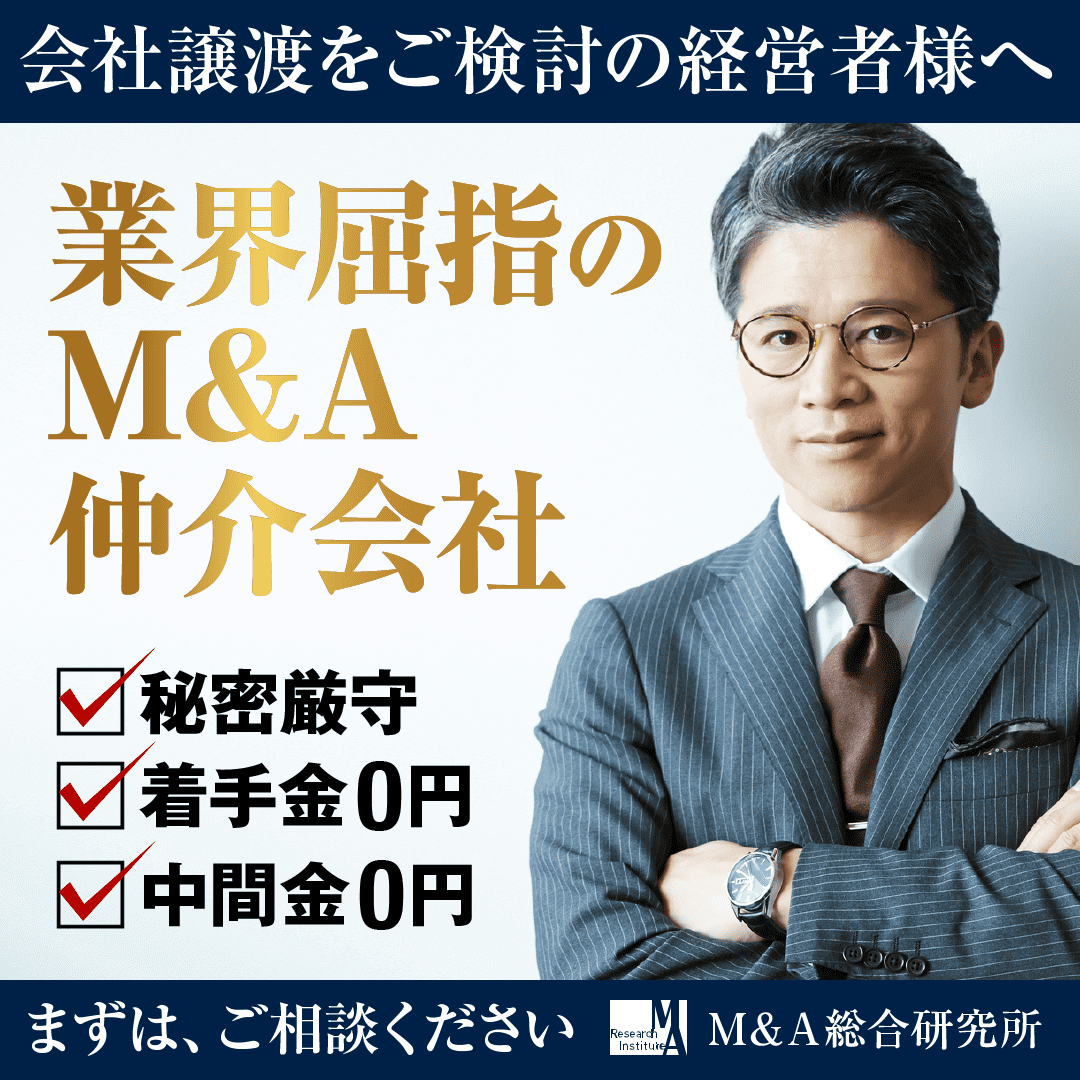2025年07月14日更新
M&Aとは?M&Aの意味や流れ・メリット・手法などわかりやすく解説!
M&Aとは、日本語では「合併と買収」という意味です。さまざまなM&A手法があり、成功によって得られるメリットも異なります。この記事では、M&Aとは具体的にどのような行為を意味するのか、手法ごとの流れやメリット、成功ポイントを解説します。
目次
1. M&Aとは?
M&Aとは、企業の合併と買収を意味する言葉です。もともと外国企業を中心に経営戦略の1つとして活用されていましたが、近年は日本国内の企業も積極的にM&Aを行うようになってきました。
事業や企業の成長・発展を目的としてM&Aを活用するケースが多く、中小企業の場合は事業承継目的でのM&A割合が高く、年々その数も伸びています。
M&Aの意味
M&Aの正式名称はMergers and Acquisitionsであり、読み方は「マージャーズ・アンド・アクイジションズ」です。
それぞれ、Mergers=合併、Acquisitions=買収という意味の英単語であり、M&Aとはこの2つの単語の頭文字を取った言葉で「エムアンドエー」と呼ばれます。
M&Aという場合、狭義的には「合併」に該当する吸収合併と新設合併と「買収」で用いられる株式譲渡・事業譲渡・株式交換・第三者割当増資などを指します。
また、企業同士が協業する資本提携(あるいは業務資本提携)なども、広義的な意味でM&Aに含むことも多いです。
事業売却については以下の記事で詳しくご説明していますので、そちらもご一読ください。
会社売却については以下の記事で詳しくご説明しています。ぜひご一読ください。
2. M&Aの目的
企業がM&Aを行う理由・目的にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは売却側(譲渡側)・買収側(譲受側)に多くみられる目的を紹介します。
売却(譲渡)側のM&A目的
売却(譲渡)側がM&Aを行う目的には、主に以下の3つがあります。
後継者問題の解決
中小企業の場合、自社の存続を希望していても、経営者の周りに後継者候補となる人物がいないために廃業せざるを得ないケースもみられます。M&Aは事業承継の手段としても活用することができ、第三者(法人あるいは個人)へ自社を売却することで事業承継が可能です。
日本の企業は9割以上が中小規模の事業者ですが、経営者の平均年齢は年々あがっており、団塊世代の多くが引退のタイミングを迎える2025年には70歳以上の経営者は250万人にもなるといわれています。
中小企業の存続は日本経済にも大きな影響を与えるため、後継者問題の解決は国の大きな課題であり、M&Aはその有効な手段といえるでしょう。
経営基盤強化
特に中小企業の場合は、自社の資金力のみでは事業の発展が難しいケースもあるでしょう。そのような理由から、経営営基盤強化を目的としてM&Aが行われるケースもあります。
売却(譲渡)側企業はM&Aによって買収側(譲受側)企業のリソースを相互活用できるようになり、経営基盤の強化が可能です。さらに、ノウハウや技術を組み合わせたり、販路や顧客を共有したりすることによって、シナジー創出にも期待できます。
また、複数事業を手掛けている企業の場合は、事業譲渡などのスキームを用いて不採算事業のみを切り離す(譲渡する)ことも可能です。
創業者利益の獲得
創業者利益の獲得を目的にM&Aを行うケースも多いです。株式譲渡の場合は、譲渡対価(現金)を株主であるオーナーが受け取ります。
中小企業の多くは非上場であり株式の現金化が難しいですが、M&Aによる株式の譲渡では対価として現金を得ることが可能です。実際に引退後の資金確保のために自社を売却するケースや、得た利益を資金として新たに事業を始めるケースも多くみられます。
買収(譲受)側のM&A目的
買収側(譲受企業)がM&Aを行う目的としては、主に以下の4つが挙げられます。
事業の拡大
買収(譲受)側はM&Aによって既存事業の拡大や強化が実現可能です。同業種の企業を買収した場合は、売却(譲渡)側企業の保有シェアをそのまま獲得できます。
また、自社と関連性の高い事業を買収すれば、顧客や技術・ノウハウなどを獲得でき、事業領域の拡大を図ることも可能です。
優秀な人材の獲得
売却(譲渡)側企業の優秀な人材をまとめて獲得できる点も、買収(譲受)側の大きなメリットです。介護施設や調剤薬局、建設業などのように有資格者がいなければ業務を行えない事業もあります。
事業に必要な有資格者を新規採用することもできますが、十分な人数が確保できるとは限らないうえ、採用した人材のスキルや経験が不足している可能性もあるでしょう。
売却(譲渡)側企業の人材を引き継ぐ方法はM&Aスキームによって異なり、株式譲渡の場合は特別な手続きを行わなくても買収(譲受)側は雇用契約を引き継ぐことができます。
事業譲渡を用いた場合は雇用契約の結びなおすかたちとなり、その際は従業員の個別同意が必要です。
新規事業参入
新規事業への参入をスムーズに行うことを目的に、その業界で事業展開している企業を買収するケースも多いです。新規事業の立ち上げには資金と時間が必要であり、事業がうまく軌道に乗るかどうかというリスクもあります。
M&Aで新規参入したい業界で事業展開している企業を買収すれば、顧客や販路、技術・ノウハウなどがある状態で事業を始めることが可能です。
シナジー効果
M&Aで得られるシナジー効果には「販売シナジー」「生産シナジー」などさまざまなものがあります。設備や販路などの共有による業務効率化や、原材料を大量に仕入れることによるコスト削減などはその一例です。
売却(譲渡)側企業とのシナジー効果創出を目的として買収が行われる事例は非常に多く、シナジーが十分に発揮されればM&A後の事業成長・発展に期待できます。
3. M&Aのメリット
M&Aにはさまざまなメリットがあり、成長戦略や事業承継の手段として活用されるケースが年々増えてきました。ここでは、売却側・買収側のそれぞれのメリットを解説します。
| 売却側のメリット | 買収側のメリット |
|
|
売却側のメリット
M&Aによる売却側のメリットは、主に以下の4つがあります。
①後継者問題の解消
近年は後継者問題に悩む中小企業も多いですが、M&Aによる事業承継(売却)は経営者の周りに後継者がいない場合に有効な手段です。
小牛高齢化が進む日本では、経営者に後継者となる子がいないケースや子が別の企業務めているなどにより引継ぎが難しいケースもみられます。
そのため、経営者が高齢になり引退のタイミングを迎えても、事業承継できない企業も多いのが実情です。中小企業の事業承継は国の課題でもあり、スムーズな事業承継ができるようさまざまな施策も設けられています。
施策にはM&Aに対する制度もあり、後継者候補がいない場合はM&Aによる第三者へ自社を売却することで事業承継が可能です。
②従業員の雇用確保
M&Aは単に事業や企業を売却する行為ではなく、自社の従業員や経営資源なども譲渡・売却の引継ぎ対象です。
廃業という選択をすれば従業員を解雇することになりますが、M&Aであれば従業員の雇用を買収側企業へ引き継ぐことができます。
また、株式譲渡を用いる場合は従業員の雇用だけでなく、取引先・仕入先・顧客なども包括承継される点もメリットです。
③経営者の個人保証の解消
経営者自身が会社の負債の連帯責任者となっている場合、リスクを心配して事業承継や廃業に踏みきれないというケースも多いです。
M&Aによる事業承継では、使用する手法や契約内容次第で経営者の個人保証も解消されます。個人保証からの解放は経営者にとって心理的にも経済的にも大きなメリットといえるでしょう。
④資金調達の実現
元来、M&Aとは、業績不振などの理由で仕方なく企業を売却するといった行為ではありません。過去の事例を見ると、本業や中核事業などに集中する目的で他の事業を売却する企業も多く存在します。
資金ショートする前の対策としてM&Aをする企業もあります。
そのような事業譲渡では、本業以外の事業を売却すれば資金が得られるため、本業への資金に充てることが可能です。
また、株式取得による資本参加というスキーム(手法)の場合、売却後も経営に関われます。財務基盤が安定している企業の傘下となれば、事業の拡大を容易に実現できるメリットも期待可能です。
買収側のメリット
M&Aによる買収側のメリットには、主に以下の4つがあります。
①技術獲得
技術獲得には、ノウハウの獲得も含まれます。そもそも企業は、新規事業へ進出する際に新たな商品・サービスの開発が必要となる場合が多いですが、それには技術・ノウハウが不可欠です。
M&Aによる買収で技術・ノウハウを獲得できれば、新規事業にスムーズに進出しやすくなります。
②人材確保
会社を経営するうえで、最も重要となる資源は人材です。技術・ノウハウと合わせて人材も確保できれば、企業が事業を進めていくうえで非常に有利な条件がそろいます。
また、自社のコア事業に弱みがある場合にも、人材確保によってネガティブ要素の改善が見込むことが可能です。
③事業の多角化
買収側は、M&Aにより多角化経営の実現および隣接事業への進出が可能となります。なぜなら、M&Aでは、シナジー効果の獲得を期待できるためです。
シナジー効果とは、相乗効果のことです。例えば、不動産業を手掛ける企業が小売業を買収すると、シナジー効果により両社の持つ広告口が広がるため、売上を伸ばすことが可能です。
その他にも、互いの事業が良い影響を及ぼし合うことで、それぞれの売上が更に伸びるケースは多々あります。
④コストの削減
既存事業のシェアを拡大できれば、「規模の経済」が働いて仕入れ・運用に関するコストを削減できます。これは、買収対象会社の取引先・顧客などの承継により生まれるメリットであり、短期間で事業拡大を実施可能です。
また、品質管理・物流・販売の各部門を一元化できれば、生産性の向上も期待できます。
M&Aのメリットを知りたい方は下記の記事で詳しく説明しています。ぜひご一読ください。
4. M&Aのデメリット
M&Aにおける買収側の主なメリット・デメリットには、以下のものがあります。
| 売却側のデメリット | 買収側のデメリット |
|
|
売却側のデメリット
M&Aによる売却側のデメリットには、主に以下の4つがあります。
①従業員の労働条件が悪くなる可能性
M&A後、経営統合プロセス(PMI=Post Merger Integration)の過程で、買収側の人事規定にのっとって売却側従業員の雇用・労働条件は変更されるのが常です。多くの場合、買収側の方が経営規模も大きく、雇用・労働条件は改善される傾向にあります。
しかし、中小企業であった売却側においては、就業規則などの内部規定が不十分であることがあり、買収側の大手企業の内部規定はきちんとした定めがあることから、新たな労働条件を不満に感じるかもしれません。
個人によっては、雇用・労働条件が悪くなったと思う従業員が出る可能性もあります。この場合、その従業員は離職してしまう可能性もあり、PMIにおいて、どれだけケアできるかが課題です。
また従業員の雇用条件についてはM&Aの最終契約書において、条件が悪くなるような変更をしばらくの間はしない、ということを定めることもできます。
買い手企業を探す段階において、こういった内容を理解してくれる会社を探すということもM&A成功のポイントの一つです。
②売却先の企業が見つからない可能性がある
自社の売却を検討しても、売却先企業が見つからない限りM&Aを進められません。経営者が自社に対してどれだけ時間や資金を費やしてきたとしても、M&Aにおいて評価されるのは、将来的に事業がどれだけ利益を生むのか・どれだけの価値があるのかという点が中心です。
自社に見合った買い手企業を見つけるには、事前にM&A仲介会社などの専門家に相談したうえで、希望額の設定・譲渡内容を含めたM&A戦略を十分に練ることが必要となります。
③取引先の反発や契約の打ち切り
買収によって取引先との契約条件変更や担当者変更などが生じた場合、長期にわたって良い関係を築き上げてきた取引先から反発されることがあり、場合によっては契約を打ち切られる可能性もあります。
特に中小企業の場合は、オーナーが個人的に取引先と付き合いがあり、それにより良い条件で契約ができていた場合などは、オーナーが代わることで契約条件もこれまで通りにはいかないということも考えられます。
M&Aでは会社の収益性を見込み評価で判断するケースもあるため、後のトラブルで企業価値を低下させないように注意が必要です。
またそうならないように、取引先への説明なども慎重に行う必要があります。M&A実行後には新しい担当者と一緒に取引先に挨拶に行くなどし、時間をかけて引き継ぐことが重要です。
④企業文化の統合による障害
M&Aとは、異なる企業文化を持つ会社同士が1つになる行為であるため、統合がうまくいかなければ弊害が生まれやすくなります。M&A後における企業文化の融合は、時間をかけて入念に進めていくことが必要です。
融合がうまくいかなければM&A自体が失敗に終わるケースもあるため、従業員の仕事に対する考え方・姿勢・判断軸などを十分に考慮したうえでM&Aを進めていきましょう。
買収側のデメリット
M&Aによる買収側のデメリットには、主に以下の4つがあります。
①収益化できるか不確実
M&Aとは、事業拡大・新規事業への参入など主として収益拡大を目的として実施されるものですが、事業・会社を買収したからといって、必ずしも収益化に成功するとは限りません。
M&Aでは契約条件次第で売却側の負債(簿外債務を含む)などを引き継ぐため、取引対象を十分に認識しないまま承継すると、収益化できないばかりか不利益を被るおそれもあります。
上記のリスクを回避するには、M&A前に財務デューデリジェンス(DD)を念入りに実施すると良いでしょう。
②優秀な人材の流出
M&Aでは売却側の優秀な人材やノウハウなどを獲得できますが、M&A後に売却側の人事制度・会社の風習・評価制度などを変えると、優秀な人材を流出させてしまうおそれがあります。
M&A後の労働条件変更・統合や買収後の派閥争いなどは従業員に不信を抱かせる原因となるため、M&Aによる買収を進める場合には人事デューデリジェンス(DD)を入念に行い、その内容を企業統合プロセス(PMI)に反映させると良いでしょう。
特に既存の従業員に不利にならないようにすることが重要です。
③シナジー効果が得られない
シナジー効果とは相乗効果のことであり、十分に発揮されると足し算以上の成果をもたらします。しかし、M&Aで組織が拡大すると意思決定のスピードが遅れてしまい、企業の弱体化と企業価値の低下を引き起こすおそれもあるのです。
つまり、M&A後に生じる部署ごとの連携不足・企業文化の違いなどは、シナジー効果獲得に失敗する原因となります。こうした事態を避けるには、企業統合プロセス(PMI)を慎重に行うと良いでしょう。
④買収先企業との融合がうまくいかない
たとえM&A後の人材流出が避けられたとしても、M&Aは社風や従業員の待遇が異なる企業同士が統合する行為であるため、企業文化の違いにより会社内での融合がうまくいかないこともあります。
このような事態に陥ると、事業拡大までに時間や費用が必要以上に発生するうえに、その後の企業運営が円滑に進まない可能性も高まるでしょう。M&Aを実施する際には、この点を踏まえて、なるべく自社と類似する文化を持つ企業を買収するのが良策です。
5. M&A成功のためのポイント
M&Aを成功させるためには、どのような点を意識して進めていけばよいのでしょうか。ここでは、M&A成功のためのポイントを解説します。
相手企業とのマッチング
自社に合った相手先をみつけることは、M&Aを成功させるうえで欠かせない要素です。どのような企業が相手先に最適なのかは、現状の課題や自社の強み・弱みによって変わってきます。
どれだけ知名度や資本力がある相手先でも、自社にとってベストな相手先とは限りません。マッチング前の希望条件設定では、まず自社の課題・強み・補完したい弱みなどを改めて整理し、必要なリソースがなにかを明確にすることがポイントです。
一般的にM&Aでよい相手先になりやすいのは「シナジーが創出しやすい」「相互補完ができる」「企業風土が似ている」の3つを揃えている企業といわれます。
条件交渉
よい相手先をみつけても、M&Aの希望条件やスタンスによっては本来の目的が果たせない可能性もあります。特に意識しておくべき点は以下の3つです。
- 売り手企業と買い手企業は対等な立場であることを意識する。特に買い手企業は「大切な会社を譲り受ける」という心構えをもつことが大切。
- 買い手企業は売り手企業の実態を可能な限り早期に把握し、買収費用に見合う効果がM&Aによって得られるか見極める。
- 買い手企業は買収のリスクをデューデリジェンスによって洗い出し、回避策によって許容範囲内に抑えられるかを見極める。
M&A後の経営統合プロセス
M&Aは成約後の経営統合プロセス(PMI)がスムーズに進み、シナジーなどの期待していた効果が十分得られてこそ成功したといえます。経営統合プロセスを進めるうえ重要となるのは以下の2点です
- 買い手側は売り手企業へ派遣する人材(次期社長や重職ポストなど)選定を慎重に行う
- 従業員のモチベーション(特に売り手側の従業員)士気向上に努める
経営統合プロセスは、買い手・売り手が協力して進めていかなければ成功しません。どのように経営統合プロセスを進めていくべきかはM&A後に検討するのではなく、M&Aを検討する段階から視野に入れておくことも重要なポイントです。
6. M&Aの流れ(手順)
M&Aスキーム(手法)によって細かな部分は異なるものの、大まかな流れは共通しています。ここでは、M&Aの流れ(手順)を解説します。
検討
まず「なぜM&Aを行うのか」を明確にし、M&A後のビジョンを描き方向性を検討することが重要です。M&Aを行う目的や方向性が明確になっていないままM&Aに取り組んでしまうと、判断を誤ってしまったりM&Aを成約させることが目的に変わってしまったりする可能性もあります。
満足度の高いM&Aを実現させるためには、自社がM&Aを行う目的をしっかり定めておくことが必要です。買収側企業はM&A後の成長戦略を明確にしたうえで、交渉相手への希望条件や使用スキームなどを検討段階である程度絞り込んでおくとよいでしょう。
売却側企業は、譲渡希望価格の設定・従業員や役員などの雇用・売却時期など目標や希望条件を検討します。また、M&A仲介会社への相談やM&Aの交渉を見据えて、自社の強みや弱みを整理しておくとよいでしょう。
M&A仲介については下記の記事で詳しく説明しています。ぜひご一読ください。
準備
次は、M&Aの方向性や将来の目標などを踏まえて具体的なプランを決めていきます。M&Aでは戦略作成が重要となるため、M&A仲介会社などの専門家と相談しながら進めていくかたちが一般的です。
この段階では、企業価値評価(バリュエーション)や企業概要書の作成も行います。企業価値評価(バリュエーション)は価格交渉のベースとなる株価、簡単にいえば「会社の値段(価値)」を算出することです。
大きく分けてコストアプローチ・インカムアプローチ・マーケットアプローチの3つがあり、それぞれに複数の算出方法があります。それらを用いて企業価値を求め、実態を把握したうえでM&Aの条件を固めていきます。
企業概要書は「売却側企業の情報をまとめた提案書」であり、企業沿革・事業内容・組織体制・財務状況・取引先(顧客)・業務フロー・株主構成など、詳細情報を要約したものです。
M&Aは面識のなかった企業同士が行うケースが多いため、売却側企業の魅力や強みが正しく伝わるよう企業概要書を作成します。
M&Aの準備をしっかり行い計画的に進めていくことが重要です。企業価値評価だけでなくM&A仲介会社などの専門家は企業価値評価だけでなく企業概要書作成のサポートも行っているので相談しながら進めていくとよいでしょう。
相手探し
M&Aを行う準備が整ったら次は交渉先となる企業を選定していきますが、選定時のポイントは売却側・買収側とで異なります。まず、売却側企業が見極めるべきポイントは「社風や経営理念」「事業規模や業績」「業種」の3つです。
社風や経営理念がかけ離れている場合は、M&A後のPMIがうまくいかない可能性もあります。書面から受けるイメージだけでなく、実際のトップ面談でしっかり見極めることが重要です。
また、業種については同業種か異業種化で想定されるシナジー効果が大きく違ってきます。自社がM&A(売却)を行う目的だけでなく買収側の目的も念頭におき、最初は広い視野で検討するとよいでしょう。
一方で買収側が意識すべき点は「成長戦略」「想定されるシナジー効果」「事業承継」です。特にどのようなシナジーが見込めるかはM&A後の事業成長・発展に大きく関与します。売却側企業の事業内容や強みなどを理解したうえで、本格的な交渉へ進むかを検討していくとよいでしょう。
買い手(売り手)へのアプローチ
まずは、M&A相手候補となる法人・個人を見つけてアプローチするプロセスです。譲渡・譲受先となり得る候補先をM&A仲介会社やアドバイザーなど専門家にリストアップしてもらいながら、自社の希望条件に合う候補を決めていきます。
売り手側からは「ノンネームシート」と呼ばれる書類を開示し、買い手側ではノンネームシートの内容を見て検討を進めていく仕組みです。
ノンネームシートは匿名状態で企業概要が記載されており、財務状況や簡単な事業内容などが盛り込まれます。
ノンネームシートだけではどの企業かは特定できない情報量ですが、それでいて買い手側が進めるかどうかをある程度判断できる程度の材料を記載します。
IM(Information Memorandum)の提示
売却側の場合、ノンネームシートを提示して買い手側企業が詳しい情報を求めてきたら、秘密保持契約(NDA/CA)を企業間で結んだうえで、IM(Information Memorandum)を提示します。
IMは日本語表記で「インフォメーション・メモランダム」と呼ばれる企業概要書のことであり、会社の名称・詳細な事業内容・財務情報などが記載される書類です。IMを見た買い手企業は、M&Aについて具体的に検討していきます。
トップ面談(経営者同士の面談)
経営トップ同士の面談は、互いの人となりや経営理念など書面ではわかにくい部分を確認しあい理解を深める場として設けられます。トップ面談では譲渡金額や従業員の処遇など条件交渉はせず、M&A後のビジョンや想定されるシナジーを明確にすることを念頭におき臨むことがポイントです。
また、自社が売却側・買収側のどちらであっても「対等な立場」で相手企業のトップと接するよう心がけましょう。トップ同士の面談はM&Aプロセスで必ず行われるものであり、M&Aの成否を左右する重要な機会です。
買収・売却の検討に至った経緯・経営で大事にする信念などを共有できれば、M&Aにおいて最も大切となる信頼関係を構築できます。
トップ面談の後に、買い手側がM&Aに前向きである場合、LOI(Letter of Intent=意向表明書)を売り手に提出するケースもありますが、必須というわけではありません。
基本合意締結
諸条件・使用スキーム・譲渡価額などについて両社が大筋で合意したら、基本合意書を作成して締結します。基本合意の締結は「破談になるような大問題がない限りM&A成約(最終合意契約)に向けた交渉を続ける」と意思表示をしたということです。
そのため、締結する前はもう一度よく検討することが重要となります。売却側企業は「自社を任せられる企業なのか」「従業員の雇用はしっかり引き継いでもらえるか」「企業風土が合うか」などが確認すべきポイントです。
買収側企業は「買収によって得られるシナジー効果はどのくらいなのか」をしっかり検討し、そのうえで買収の運営体制や引継ぎの方法や期間などもある程度詰めておく必要があります。
また、基本合意書はあくまでもその時点での合意内容であり、M&A成約を保証するものではありません。基本合意書そのものに法的拘束力はなく、デューデリジェンスの結果によっては条件や価格の変更されたり、大きな問題があったりした場合はM&A取引が中止となる場合もあります。
ですが、買収側に付与される独占交渉権など一部条項については、法的な拘束力を持たせるケースがほとんどです。
デューデリジェンス(DD)の実施
トップ面談により基本合意を締結した後は、デューデリジェンス(DD)を実施します。デューデリジェンス(DD)とは、売り手企業の状況把握を目的とする精密調査であり、買い手企業が専門家に依頼したうえで実施するケースがほとんどです。
DDには主に財務DDや法務DDなどがあります。財務DDでは公認会計士や税理士などが売り手企業の財務資料を細かく調査し、財務の問題が無いかなど細かく確認します。
法務DDでは主に弁護士が売り手企業の法務面や、契約書周りなどを細かく確認します。
ここで基本合意までに未開示であった問題が発覚したり、顕在化していなかったリスクが明らかになったりすると、M&A取引自体が破談になりかねないため注意しましょう。
最終条件交渉
デューデリジェンス(DD)の結果、買収側がM&Aを成立させて問題ないと判断すれば、最終条件交渉へ移ります。この条件交渉はデューデリジェンスを内容を踏まえて行う、M&Aの最終局面です。
重大な決断がを行う場面では焦ってしまったり気持ちが大きく揺れたりすることもあるかもしれません。スムーズに最終交渉を進めいくためにも、売却側企業・買収側企業はそれぞれ以下の点に注意が必要です。
| 売却側の注意点 | 買収側の注意点 |
|
|
自社を売却することは売却企業の経営者にとって大きな決断となるため、最終契約が目前に迫り「本当にこの選択がよいのか」と悩み、第三者に意見を求めるケースもあるでしょう。
しかし、決断にかける時間が長すぎれば買収側企業がM&A交渉を中止する可能性もあります。売却側の経営者は最終決断は自身で下すことをしっかり認識しておくことが重要です。
買収側にとってM&Aのリスクを最小限にとどめたいと考えるのは当然ですが、リスク回避を意識するあまり無理な条件ばかりを要求すれば、交渉がまとまらず破談になる可能性もあります。「M&Aはリスクがあること」を覚悟することも買収側には必要であり、そのうえで最終的な決定を行うことが重要です。
最終契約
条件交渉によりお互いの認識に相違がなければ、最終契約のプロセスに移行します。以降の手続きでは取締役会・株主総会などでの議決が必要となるため、自社内でも各種準備を進めておかなければなりません。
最終契約書の締結
M&Aの最終契約はDA(Definitive Agreement)とも呼ばれ、M&Aスキーム(手法)によって「株式譲渡契約書」「事業譲渡契約書」などの契約書を作成し締結します。
最終契約書に記載する主な内容は、譲渡対象・売買価額・対価の支払い方法・表明保証・クロージングなどです。最終契約書はそのすべての事項に法的拘束力があり、締結後の一方的な変更や解除は特別な理由がない限り認められません。
最終契約書の締結にあたり、買収側は表明保証に関する事項が盛り込むことが重要です。表明保証とは売却企業が交渉中に開示した一定の事項(財務や法務など)が真実であることを保証するものであり、M&A後に保証違反があれば損害賠償を請求することができます。
売却側はクロージングの条件をしっかり確認しておくことが重要です。最終契約書で取り決めた条件を満たしていない場合は決済(引き渡しと対価の支払い)は行えず、最悪の場合はM&Aが白紙撤回される恐れもあるため、注意して確認するようにしましょう。
社内外の関係者へ情報開示
最終契約書の締結後は、できる限り早く社内外の関係者へM&A実施についての情報開示を行います。 情報開示が必要となるのは、従業員・取引先や顧客・取引している金融機関などです。
どのタイミングで情報開示を行うかは事情によって異なるため、事後のトラブルが生じないよう、M&Aの当事会社や関係者間で協議して慎重に進めるようにしましょう。
特にキーパーソンや有資格者など事業に不可欠な人材が離職してしまうと、M&A後の事業運営にも支障をきたす可能性もあります。M&A後の事業運営がスムーズに進むよう、丁寧に説明し十分理解を得ることが大切です。
経営統合作業(PMI)
譲渡金の受け取り・企業や事業の受け渡しなどが済むとM&A取引が完了し、PMIプロセスに移行します。PMI(Post Merger Integration)とは、日本語表記で「ポストマージャーインテグレーション」と呼ぶ、M&A後の経営統合プロセスです。
PMIの目的は、経営戦略やビジョンの浸透・生産性向上・コスト削減・従業員のモチベーション維持、向上です。そのため、M&A実施後の企業に新たな組織体制を構築するために重要なプロセスです。
7. M&Aのスキーム(手法)
M&Aには、大まかに分けると合併・買収・分割という3つのスキーム(手法)があります。これらの大まかなスキームは、事業譲渡や株式譲渡のように、さらに細かく分類されているのです。
この章では、M&Aの理解をより深めるため、M&Aのスキームを解説します。
| 企業提携 | 資本の移動を伴う企業提携 ※広義のM&A |
企業買収 ※狭義のM&A |
買収 | 株式取得 資本参加 |
株式譲渡 |
| 株式交換 | |||||
| 新株引受 | |||||
| 事業譲渡 資産買収 |
全部譲渡 | ||||
| 一部譲渡 | |||||
| 分割 | 吸収分割 | 分社型分割 | |||
| 分割型分割 | |||||
| 新設分割 | 分社型分割 | ||||
| 分割型分割 | |||||
| 合併 | 吸収合併 | ||||
| 新設合併 | |||||
| 株式の持ち合い | 業務提携の強化 | ||||
| 合弁会社の設立 | リスク分散 | ||||
| 資本の移動を伴わない企業提携 ※業務提携 |
販売提携 | 営業・販売部門の強化 | |||
| 共同開発・技術提携 | 研究・開発部門の強化 | ||||
| OEM提携 | 工場・生産部門の強化 | ||||
買収
買収は、英語で「Acquisitions」と表記し、日本語で「アクウィジション」と表記します。買収とは、一方の企業がもう一方の企業の議決権を過半数以上取得するなどして、企業(事業)を買い取るスキームです。
買収は経営の効率化・新規事業への進出などの目的で実施されるスキーム(手法)であり、他企業の事業部門や営業権などのほか、ノウハウ・技術を持つ企業自体の買収が目指されることもあります。ここからは、代表的な買収のスキームを細かく紹介します。
株式譲渡
株式譲渡は、買収の中でも「株式取得」に分類される手法の一つです。
譲渡企業のオーナーが、保有株式を第三者に譲り渡すことで、経営権を移譲する手法です。
手続きとしては、売り手と買い手が株式譲渡契約書を取り交わし、株主名簿を書き換えるだけで済むシンプルな方法で、中小企業のM&Aでは最も多く活用されている手法です。
株式譲渡についてについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
事業譲渡
事業譲渡は、企業が保有する事業の一部または全てを売却するスキーム(手法)です。主として、不採算事業の整理を目的とする企業再編などにおいて採用されています。
株式の異動を伴わないため、M&A後も売却側企業はそのまま会社運営ができ、反対株主がいる場合も行いやすい点がメリットです。
一方で、買収側企業は自社に必要な事業のみを取得することができます。株式譲渡と違い個別承継となるため、債務などのリスクを引き継がなくて済み、損金算入できるので節税効果(法人税)がある点もメリットです。
事業譲渡についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご一読ください。
第三者割当増資
第三者割当増資は、企業が新株を発行して、既存の株主以外の第三者にその株式を割り当てる手法です。
資金調達方法としても広く利用されている手法で、結果として既存株主の持株比率は下がることになります。
M&Aにおいては、第三者割当増資によって第三者が発行済株式の3分の2以上を取得する目的で実施されることが多く、実質的にこの第三者が経営権を得ることになります。
株式交換
株式交換は、ある会社を100%子会社化するために用いられる手法で、買い手企業が売り手企業の株式を100%取得する代わりに、買い手企業から売り手企業のオーナーに対価が支払われます。
この対価には買い手企業の株式が用いられることが一般的ですが、他に現金を交付するなどの手法もあります。
買い手から見れば、自社の株式を譲渡対価として用いる場合には買収資金を用意しなくても良いというメリットがあります。
株式交付
株式交付は2021年3月に施行された会社法の改正によって新しく創設された制度です。
株式交換とよく似た手法で、売り手企業の株式を取得する代わりに、買い手が自社の株式を売り手企業のオーナーに渡すという手法です。
株式交換とは異なり、子会社化を目指す限り、100%子会社化を目的としない場合でも適用が可能です。なお、株式交付は外国会社の買収には使えません。
株式公開買付(TOB)
株式公開買付(TOB)は、英語で「Take Over Bid」と表記し、日本語で「テイク オーバー ビット」と表記します。
株式公開買付(TOB)は、買収先企業の株式取得を公告したうえで、不特定多数の株主から金融商品取引所を通さず直接的に株式を取得するスキーム(手法)です。
株式公開買付(TOB)では、一般的に、金融商品取引所における取引価額よりも上乗せされた価額により買付が実施されます。
経営陣買収(MBO)
経営陣買収は、英語で「MBO:Management Buyout」と表記し、日本語で「マネジメントバイアウト」と表記します。経営陣買収(MBO)は、経営陣が自社株式を買収するM&Aスキーム(手法)です。
具体的には、経営陣が自己資産、またはそれが足りない場合には銀行や投資ファンドから資金調達を行ったうえで、自社株式を取得します。
短期志向の株主・投資家などの意見に左右されることなく、中長期的な経営戦略の実施および意志決定の迅速化などが図られるため、経営体制の見直し・上場企業に課せられる情報公開の厳格化などへの対応策として注目されるスキームです。
なお、経営陣ではなく従業員が自社株式を買収するケースもあり、その場合はエンプロイー・バイアウト(employee buyout)と呼ばれます。
合併
合併は、英語では「Mergers」と表記し、日本語では「マージャーズ」と表記するスキーム(手法)です。合併では複数の会社が1つに統合され、上図のように吸収合併と新設合併の2種類があります。
第三者の関係(グループ会社間ではない)企業間が合併を行う場合、事前に株式譲渡で100%子会社化してから合併を実行するケースも多いです。
吸収合併
吸収合併は、英語で「Absorption-type Merger」と表記し、日本語で「アブソープション(タイプ)・マージャー」と表記します。
吸収合併は、一方の法人格を残しながら、もう一方の法人格を消滅させるスキーム(手法)です。合併により消滅する会社の権利・義務の全ては、合併後に存続する会社へと引き継がれます。
新設合併
新設合併は、英語では「consolidation-type merger」と表記し、読み方は「コンソリデーション(タイプ)・マージャー」です。
新設合併は、事業における権利・義務を引き継ぐ会社を新たに設立し、もともと事業を行っていた法人は承継後に消滅します。
分割
分割は、会社の事業に関する権利義務の全部または一部を他企業に承継させる組織再編行為です。会社分割は、上図のように新設分割と吸収分割の2種類に分けられます。
新設分割
新設分割は、会社分割により新しい会社を設立したうえで、新設会社に既存会社の特定の事業や資産を承継させるスキーム(手法)です。
M&Aで会社ごと譲渡するのではなく、会社の中の特定の事業のみを第三者に譲渡する場合に用いられることが多いです。
また、M&Aに限らず、グループの中で組織再編を行う場合にも用いられることがあります。
吸収分割
吸収分割とは、ある会社の特定の事業や資産を切り出して、既存の他の会社に承継させる手法です。
新設分割が会社を新設する手法であるのに対して、吸収分割は既存の会社に事業を移すという違いがあります。
事業譲渡とよく似た手法ですが、事業譲渡の場合は債権者や従業員、取引先の個別の同意が必要であるのに対して、吸収分割の場合はそれを必要とせず、承継が可能です。
そのため吸収分割の場合はコストがかからず、M&Aで用いられることも多いです。
8. M&Aスキームを選ぶ基準
紹介したようにM&Aスキームにはさまざまなものがあり、それぞれ効果が異なります。自社の目的に合ったもの手法を選ぶことが重要です。
対価の受け取り対象と課税対象
M&Aは手法によって対価を受け取る対象が変わり、課税対象と課税率にも違いがあります。実際に用いられることの多い3つの手法で、対価を受け取るのは以下の対象者です。
- 株式譲渡:売却側企業の株主(オーナー経営者)
- 事業譲渡:売却側企業(対価は会社へ入る)
- 会社分割:売却側企業(対価は会社へ入る)
M&A手法を決める際は「誰が対価を得るのか(得たいのか)」を考えて検討する必要があります。また、M&Aは取引額が大きくなるため税負担も重くなりやすいため、検討時は課税対象者と税率についての考慮も必要です。
手続きやスケジュール
M&Aの大まかな流れはどの手法を用いても同じですが、必要な手続きが異なるため手間や時間の部分は大きく変わります。たとえば、株式譲渡の場合は、株主構成が変わるだけなので対象会社に大きな変更が生じることはなく、必要な手続きは株主名簿の書き換えだけです。
そのため、ケースによっては最終契約とクロージングを同じタイミングで行うこともあり、比較的短い期間でM&Aができます。一方で事業譲渡では個別承継と呼ばれる引継ぎ方法となり、従業員や取引先との契約は買収側が改めて結びなおすため数週間~1か月程度は必要です。
また、会社分割の場合(すべてのケースではない)は「債権者保護手続」を行うことが会社法上で定められており、その期間には短くとも1か月半程度を要します。
売却や買収の時期がある程度決まっている場合は、手法に手続きやスケジュールを確認して準備を早めに行うか、状況によっては手法の変更が必要ケースもあるでしょう。
売り手側の注意ポイント
売り手側がM&Aスキームを選ぶ際は、まず売却したい対象が「会社単位」なのか「事業単位」なのかを決める必要があります。会社自体を売却する(経営権を移転させる)場合に適しているのは株式譲渡です。株式譲渡では株主が変わるだけなので、従業員・関係先や事業への影響もさほどありません。
一方、事業の一部(あるいは全部)を切り出して売却したい場合に適しているのは事業譲渡です。取引対象は事業そのものなので経営権の移転は伴わず、売り手側企業はM&A後も会社運営を続けることができますが、重要員の雇用や関係先との契約は新たにまき直しが必要であり、許認可は原則として引き継ぐことはできません。
また、対価の受け取り先が誰(どこ)になるのかも、M&Aスキームを選ぶポイントのひとつです。株式譲渡の場合はオーナー(株主)が対価を受け取るので、引退後の生活資金獲得を目的とする場合などは適しています。一方の事業譲渡では法人(会社)が対価を得るため、資金投入したい別事業がある場合などに適した手法です。
M&Aスキームを選ぶ際は、売却単位と対価の受け取り先の2点を考慮して、自社に合ったものを選ぶ必要があるでしょう。
買い手側の注意ポイント
買い手側がM&Aスキームを選ぶ際も、まず譲受したい対象が「会社単位」なのか「事業単位」なのかを決める必要があります。会社単位で引き継ぐ場合は株式譲渡が適していますが、従業員の雇用や許認可を引き継げるメリットがある一方、資産だけでなく負債も引き継がなければなりません。
簿外債務や偶発責務などが大きければM&A後の事業運営に支障をきたすおそれもあるため、慎重に判断するとともデューデリジェンスの徹底が重要となります。
事業単位で譲受したい場合は事業譲渡が適したスキームです。事業譲渡は対象事業の必要な資産・負債のみを引き継ぐことができるので、自社に不要な事業や負債を負うリスクを避けることができます。ただし、許認可は原則引き継ぐことができず、従業員の雇用は新たに結びなおしとなるため、手間と時間が必要です。
また、買収額がどの程度になるのかという点もM&Aスキームを選ぶ要素のひとつとなるでしょう。株式譲渡と事業譲渡では、株式譲渡のほうが金額が大きくなり、売り手側が優良企業であるほど株価(評価額)は高くなるため買収金額も高額になります。
したがって、買い手側は投資額の回収見込みや取得目的を考慮してM&Aスキームを選ぶとよいでしょう。
9. M&Aのバリュエーション(企業価値評価)
企業価値はM&Aの価格交渉におきて土台となるものです。企業価値評価はバリュエーションと呼ばれることもあり、算出方法にはいくつか種類があります。
| コストアプローチ | インカムアプローチ | マーケットアプローチ | |
| 特徴 | 評価時点の正味財産に着目 | 将来の収益性に着目 | 類似会社の株式市場相場に着目 |
| メリット |
|
|
|
| デメリット |
|
|
|
コストアプローチ
コストアプローチは対象企業の純資産をもとに企業価値を算出します。計算方法はシンプルで比較的簡単なうえ、客観性が高いことが特徴です。
コストアプローチには以下の3種類があり、一般的には③の方法が多く用いられます。株式市場での相場を反映させることはできませんが、営業権を含むことで譲渡企業の収益性を加味した価値の算出が可能です。
| 企業価値の評価方法 | 計算式 |
| ①簿価純資産価額法 | 企業価値=簿価純資産−簿価負債 |
| ②時価純資産価額法 | 企業価値=時価純資産−時価負債 |
| ③時価純資産+営業権法 | 企業価値時価純資産+営業利益の2~5年分 |
マーケットアプローチ
マーケットアプローチは、評価対象企業と業種・事業内容が類似している上場企業あるいはM&A成約事例(財務指標を参考とする)を比較して、企業価値を相対的に評価します。
実際に行われた事例や市場相場・トレンドなどが反映される点は大きなメリットですが、マーケットアプローチは比較対象となる類似の上場企業がみつからない場合は使用することができません。
中小企業が行っている事業内容と類似の上場企業は少ないうえ、みつかっても規模感が大きく違うため比較が難しいケースも多いです。また、ベンチャー企業などの場合はそもそも同じ事業を行っている企業がなかったり、取引事例がなかったりするケースもあります。
マーケットアプローチには主に以下の方法があり、多く用いられているのは②の類似会社比準法(マルチプル法)です。
| 評価方法 | 計算式 |
| ①市場価額法 | 企業価値=株式市場での株価(時価)×発行済み株式数 |
| ②類似会社比準法(マルチプル法) | 企業価値=指標とする一株当たりの財務数値※×倍率 ※はPER・PBR・EBITDA・税引後利益・純資産(簿価あるいは時価)など |
| ③類似業種比準法 | 評価対象企業と業種が類似する上場企業の株価平均値に、1株当たりの配当金額・簿価純資産価額・利益金額の3項目の比較結果を乗じて算出 |
| ④取引事例法 | 譲渡側企業と類似する過去のM&A事例をベースとして企業価値を比較算出 |
インカムアプローチ
インカムアプローチでは、評価対象となる企業の将来見込まれる収益性を重視して企業価値を求めます。以下3つの算出方法があり、最も多く使用されているのは「DCF法(ディスカウンティドキャッシュフロー法)」です。しかし、中小企業のM&A実務において、インカムアプローチが使用されるケースはあまりありません。
| 評価方法 | 計算式 |
| ①収益還元法 | 企業価値=平均収益÷資本還元率※ ※資本金利と長期国債の利回りに規模や経営状態などで判断したリスクを加味したもの |
| ②配当還元法 | 企業価値=将来の配当期待値÷株主資本コスト |
| ③DCF法 (ディスカウンティドキャッシュフロー法) |
企業価値=将来の予測フリーキャッシュフロー期待値÷加重平均資本コスト(WACC) の合計 ※フリーキャッシュフローの計算方法 営業利益×(1-実効税率)+減価償却費―投資支出±運転資本増減額 |
10. M&Aにかかる税金
M&Aにより事業・会社を譲渡すると売却対価を受け取るため、譲渡益に対して税金が課されます。課される税金・税率と納税者はM&A手法(スキーム)によって変わるので、M&Aを行う際はよく理解して準備しておくことが大切です。
| 株式譲渡(法人株主) | 株式譲渡(個人株主) | 事業譲渡(法人) | |
| 税金 | 法人税など | ・所得税 ・住民税 |
・法人税:29.74% ※企業規模で税率が異なる ・消費税:10% ・不動産取得税(取得対象に不動産がある場合) ・登録免許税(取得対象に不動産がある場合) |
| 税率 | 29.74% |
20.315% 【内訳】 ・所得税:15% ・住民税:5% ・復興所得税:0.315% ※復興所得税は2037年まで |
・法人税:29.74% ・消費税:10% ・不動産取得税:固定資産税評価額の4% ・登録免許税:固定資産税評価額の2% |
| 課税方式 | 総合課税方式 | 分離課税方式 | 総合課税方式 |
| 納税者 | 法人 | 個人 | 法人 |
なお、法人税の税率は企業の規模で決まり、事業年度ごとの収入によらず一定です。法人税は損益通算されるため、M&Aを行った年度に大きな損金がある場合などは課税が生じないこともあります。
また、消費税については軽減税率対象の場合は8%が適用され、土地・債権・有価証券などの非課税品目にあたる資産への課税はありません。消費税は譲受側が譲渡側へ預けるかたちとなり、譲渡側がそれを納めます。
11. M&A関連のサービス・費用
仲介会社が中小企業のM&Aでは主流
M&Aアドバイザーにはファイナンシャルアドバイザー(FA)と仲介会社がいます。
FAは売り手または買い手のどちらかの立場に立ち、依頼企業の利益の最大化のために助言を行います。大企業、特に利害関係者の多い上場企業同士のM&Aの際はFAを起用する例が多く見られます。
FAのメリットとして条件面が理想通り実現することが挙げられます。しかし、利益の最大化のために過度な要求を行い、交渉が長期化しやすことや破談になりやすい点がデメリットとなります。
一方、仲介会社は買い手、売り手双方に対して中立的で客観的な立場です。検討〜クロージングやPMIまで一連のサポートを行います。双方の条件をすり合わせ、友好的なM&Aを行うため比較的短い期間でM&Aを行うことができます。
M&Aアドバイザーについては以下の記事で詳しくご説明していますので、そちらもご一読ください。
M&A仲介会社への手数料
M&A仲介会社やアドバイザーに依頼した場合には、仲介手数料などがかかります。M&A仲介会社やアドバイザーに依頼した場合の主な手数料・経費は、以下のとおりです。
| 手数料(名称) | 内容 | 相場価格 |
| 相談料 | M&A仲介業務を依頼する前段階の相談 | 0~1万円 |
| 着手金 | M&A仲介を正式に依頼した際に生じる手数料 | 0~200万円 |
| 中間金 | M&Aの手続きが一定段階(基本合意締結後など)に達した際に生じる手数料 | 0~200万円 |
| リテイナーフィー (月額報酬) |
コンサルタント料として毎月発生する費用 | 0~200万円/月 |
| デューデリジェンス費用 | 買収監査費用(財務・法務・人事面などのリスク調査) | 調査対象(分野)数による ※買収側が負担するケースが一般的 |
| 成功報酬 | M&Aの採取契約締結時に支払う費用 ※M&Aが成立せず取引が終わった場合は発生しない |
売却価格(譲受価格)により変動 ※レーマン方式による算出が一般的 |
| 業務実行にかかる費用 | 出張費や弁護士相談料など業務実行に付随して生じる費用 | 実費 |
上記費用のうち、着手金と中間金はM&Aが不成立に終わった場合でも返還されません。また、成功報酬の算出にはレーマン方式を採用しているM&A仲介会社が多いですが、計算ベースや料率など細かな部分は会社によって異なるため、事前によく確認しておくことが重要です。
M&Aの仲介手数料についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご一読ください。
プラットフォーム使用料
「M&Aプラットフォーム」は利用者が自身で相手先を探すことができるサービス形態で、最近はその数も増えています。料金体系は運営会社によって異なりますが、売り手側は無料、買い手側にはプラットフォーム手数料や成約手数料が生するケースが多いです。
なかには、月額費用の設定があるプラットフォームなどさまざまな料金体系があります。利用する場合は事前によく確認することが重要です。
12. M&Aの成功事例5選
ここでは、実際のM&A成功事例5選を紹介します。M&Aを成功させた企業はどのような手法を用いていたのか、成功ポイントとともに把握しておきましょう。
ワキタによるニチイケアネットの子会社化
2023年3月、ワキタはニチイホールディングスの子会社であるニチイケアネットの全株式を取得して子会社化しました。ワキタは、建設機械や土木の販売・レンタル事業を主力としており、近年は福祉用具のレンタル卸業も行っています。
子会社となったニチイケアネットは、福祉用具の販売・レンタル、福祉用具関連のカタログ製作事業を手掛ける企業です。ワキタは、ニチイケアネットを子会社化することにより、福祉用具のレンタル卸業の事業エリア拡大を進めるとしています。
参考:株式会社ワキタ「株式の取得(子会社化)に関するお知らせ 」
ソニー・インタラクティブエンタテインメントによる米バンジーの子会社化
2022年2月、ソニーグループの完全子会社Sony Interactive Entertainment(以下、SIE社)は、アメリカのBungie, Inc.(以下、バンジー)の全株式を取得して子会社化すると発表しました。
SIE社はゲーム機「プレイステーション」に関連した事業を行う企業で、ハードウェアやソフトウェアなどの企画・開発・販売などを手掛けています。
子会社となるバンジーはアメリカの独立系ゲーム開発会社です。オンラインプレイゲームの「Destiny(デスティニー)」や「Halo(ヘイロー)」は世界中に多くのファンがおり高い評価を得ています。
ソニーグループはバンジーの技術力を獲得することで、成長領域に位置付けている「メタバース(オンライン仮想空間)」の関連サービスの拡充・強化が狙いです。
なお、本買収価額は36億米ドル(日本円換算で約4140億円)と発表されており、過去にソニーグループが実施したM&Aで3番目に高い金額となりました。
参考:ソニーグループ株式会社「Sony Interactive Entertainment による Bungie, Inc.の買収に関する確定契約締結のお知らせ」
ミライト・ホールディングスによる西武建設の子会社化
2022年3月、ミライト・ホールディングスは、西武建設の発行済み株式95%を取得して子会社化しました。西武建設は西武ホールディングスの子会社で、鉄道関連工事やリゾート開発などの建築・土木工事を手がけています。
コロナ禍により主力のホテル事業に大打撃を受けた西武ホールディングスは、経営改革としてカーブアウト(コア以外の事業を売却する方法)をとると決定し、本売却もその一環で実施されたものです。
ミライト・ホールディングスは通信工事業を主力としていますが近年は需要が減少しており、成長領域である街づくり関連やグリーン発電などの事業を進めています。本買収は同事業における事業成長・展開の加速が目的です。
参考:株式会社ミライト・ホールディングス「株式会社ミライト・ホールディングスによる西武建設株式会社の子会社化 及び株式会社西武ホールディングスの子会社(孫会社)の異動を伴う 株式譲渡契約締結のお知らせ」
ベネッセホールディングスによるプロトメディカルケアの子会社化
2021年5月、ベネッセホールディングスはプロトメディカルケア(現:ハートメディカルケア)を子会社化しました。
ベネッセホールディングスはグループとして教育・語学・福祉・介護などの事業を展開しており、子会社のベネッセスタイルケアは介護業界の大手企業です。
子会社となったプロトメディカルケア(現:ハートメディカルケア)介護ガイドブック「ハートページ」発行や求人サイト「介護求人ナビ」の運営を手掛けています。
本M&Aの目的は、ベネッセホールディングス介護事業におけるシェア拡大と売上向上です。
参考:株式会社ベネッセホールディングス「株式会社プロトメディカルケアの株式取得に関する 株式譲渡契約締結のお知らせ」
エレコムによるフォースメディアの子会社化
2021年5月、エレコムはフォースメディアの発行済みは全株式を取得して子会社化しました。パソコン周辺機器の開発・販売を手掛けるエレコムは、マウスやキーボードなど多くの部門で高いシェアを持っています。
近年はUSBなどの扱い、多くの分野で高いシェアを誇る大手企業です。これまではBtoC形態で事業を展開していましたが、近年はBtoB形態へと経営方針を変更し、アジア方面などでの海外展開も積極的に行っています。
子会社となったフォースメディアは、パソコン周辺機器やネットワーク関連製品を主力とし、海外製品の輸入・販売を行う企業です。また、自社で輸入した海外製品についてはサポート体制も整えています。
本M&Aの目的はエレコムはBtoBビジネスの加速です。フォースメディアを子会社化することで、販売網や海外製品に関するノウハウを獲得し売上拡大を目指すとしています。
参考:エレコム株式会社「株式会社フォースメディアの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ 」
13. M&Aの市場動向
M&Aの市場動向はどのように推移しているのでしょうか。ここでは、M&A件数の推移やM&Aが増加している背景を解説します。
M&A件数の推移
日本においてM&Aが注目を浴びるきっかけとなった事例として、1989年の「ソニーによるコロンビアピクチャー買収」や「三菱地所によるロックフェラーセンター買収」などが挙げられます。
これらの事例をきっかけに日本でもM&Aが注目されるようになり、さらに1997年の独占禁止法改正や1999年の株式交換・株式移転制度導入など、M&A関連の法改正が進んだことで実施件数は年々増加しました。
そして、2006年の会社法施行や2007年の三角合併解禁などにより、日本のM&A実施件数がピークを迎えます。しかし、2008年のリーマン・ショック以降、日本のM&A市場は一時的に落ち込みました。
2011年の東日本大震災の影響もあり、M&A件数は会社法施行前の水準まで減少しましたが、2011年以降は増加傾向に転じています。
M&Aによる事業承継を国も後押ししており、2020年には中小企業を対象としたM&Aの指針をまとめた「中小M&Aガイドライン」が策定されました。
さらに、後継者不在の中小企業を対象としたガイドラインの第1章は「中小M&Aハンドブック」という小冊子にまとめられています。このハンドブックは中小M&Aのポイントをマンガやイラストを用いてわかりやすく解説したものです。
最近では、これまで中小企業にとって馴染みがなかったM&Aは徐々に浸透してきています。2020年はコロナ禍の影響で前年より減少したものの以降は増加傾向となり、2021年は過去最多の4304件となりました。
事業承継の脱ファミリー化

帝国データバンク 「全国企業「後継者不在率」動向調査(2022)」を元に作成
出典:https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p221105.pdf
かつて日本の中小企業では、経営者の子や親族を後継者とする「親族内承継」がほとんどでした。しかし、近年は少子化などの影響で後継者候補がいないケースや、子の意思を尊重して事業を引き継がないケースも増えてきています。
帝国データバンクが行った2022年の調査(全業種・全国の27万社を対象)では、親族内承継が34.0%とほかの事業承継方法に比べ高かったものの、前年度の38.7%より4.7%減少しました。
それに対し、自社の役員や従業員を後継者とする親族外承継の割合は前年度より2.5%増加の33.9%、M&Aや出向などによる事業承継は20.3%となっています。
また、M&Aや出向などによる事業承継が20%を超えたのは、2011年の調査開始以降では初となり、近年は「事業承継の脱ファミリー化」が進んでいることがうかがえます。
参考:帝国データバンク 「全国企業「後継者不在率」動向調査(2022)」
M&A成約の業種・譲渡企業の売上規模

独立行政法人「令和 3 年度 事業承継・引継ぎ支援事業の実績について」元に作成
出典:https://www.smrj.go.jp/org/info/press/2022/ki772s0000002mv1-att/20220609_press_01.pdf
M&Aが成約に至った譲渡企業(売り手)の業種・売上規模をみると、2021年で最も多かった業種は製造業で21.7%、次いで卸・小売業の18.6% 、建設工事業の12.2%となっています。
売り上げ規模で最も割合が高かったのは3000万円超~1億円以下で34.1%、次いで1億円超~5億円以下が30.1%、3000万円以下が 30.0%となりました。
参考:独立行政法人「令和 3 年度 事業承継・引継ぎ支援事業の実績について」
M&Aの際に譲渡側の重視すること

中小企業庁「2021年度版中小企業白書」元に作成
出典:https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2021/PDF/chusho/04Hakusyo_part2_chap3_web.pdf
中小企業庁「2021年度版中小企業白書」によれば、譲渡企業(売り手)側の経営者がM&Aを行う際に重視する事項は「売却・ 譲渡後の従業員の雇用維持」です。
アンケート調査では「従業員の雇用維持」と回答したのが82.7%と最も多く、次いで「売却価格」が48.9%「自社・事業のさらなる発展」が47.6%となりました。(ただし重複回答のため合計値は100%にはならない)
この結果から、ほとんどの経営者がM&A後の従業員の雇用継続をM&A相手先への希望条件にあげていることがわかります。
参考:中小企業庁「2021年度版中小企業白書」
M&Aの歴史
最近ではビジネス市場で広く活用されていますが、M&Aがこれまでたどった歴史も紹介します。歴史を知ると現在および今後のM&A動向を理解しやすくなるため、合わせて把握しておきましょう。
M&Aは戦前期の日本においてブームだった
当時、日本は紡績業が主力産業でしたが中国・インドの台頭により輸出が伸び悩み、追い打ちをかけるように日清戦争後の原料費や賃金の高騰により生産コストが上昇しました。
この状況を打破するためにM&Aが行われ、不況時に何度も買収をすることで企業規模を拡大し、第一次世界大戦前には日本の紡績業が世界シェアのトップまで発展しています。
M&Aによる業界再編が盛んに実施された
昭和初期は財閥が大きな富と権力をもっていたため、M&A(敵対的買収も含む)も多く行われました。大正時代末期~第一次世界大戦までは電力需要が飛躍的に増加し、さらに関東大震災の被害により安全な電力化が求められるようになります。
当時は電力会社が850社もありましたが「電力戦」と呼ばれるM&A合戦の末、5つの電力会社に集約されました。電力戦が落ち着いた後は企業再生を目的とするM&Aが推進されるようになり、新たな手法である「株式交換」が誕生したのもこの頃です。
M&Aが急増している背景
M&A件数が増加する背景には、譲渡側・譲受側企業の双方でM&Aを実施する要因がある点だけでなく、日本の景気が堅調な点、堅実に経営してきた企業の財務状態が安定してきたことも関係しています。
また、国内企業にとって少子高齢化による働き手・事業の担い手(後継者)不足は大きな課題です。そのため、深刻な状況を打破し業績拡大を目指すべくM&Aを行うケースも増えており、景気が少しずつ回復基調であることも相まってM&Aへの注目度は年々上がっています。
そのほか、経営者の高齢化・事業承継問題の解決手段としてM&Aによって自社を売却するケースも増えてきました。中堅・中小企業経営者の平均年齢は年々高くなっているにもかかわらず後継者不在の企業も多く、後継者不在問題を解決する手段としてM&Aが行うケースも増えてきています。
売却側

中小企業庁 「中小企業白書 第2章 新たな担い手の創出」元に作成
出典:https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2023/PDF/chusho/04Hakusyo_part2_chap2_web.pdf
要因のひとつとして、経営者の高齢化が挙げられます。従来は親族への承継件数がほとんどであり、主として子供に会社を継がせる経営者が多くいました。
しかし、現在では自身に子供がいない経営者も少なくなく、子供がいたとしても会社を継ぐ意思がないケースや経営者自身が子供に継がせたくないと考えるケースも増えています。
帝国データバンクの「全国企業「後継者不在率」動向調査(2022年)」によると、50歳代では65.7%、60歳代では42.6%、70歳代は33.1%の経営者が後継者不在という結果となりました。
参考:帝国データバンク 「全国企業「後継者不在率」動向調査(2022)」
M&Aのイメージの改善
M&Aに対するイメージの向上も実施件数が増加した要因と考えられます。M&Aが認知拡大されたことで、かつての「乗っ取り・身売り」といったイメージは薄れてきてはいるものの、M&Aに対してマイナスイメージを抱いている人がまだまだ多いのも事実です。
しかし、M&A(売却・譲渡すること)に対するイメージを経営者の年齢別にみると、経営者の年齢が若い企業ほど10年前と比べ「プラスのイメージになった」と感じていることがうかがえます。
M&Aは経営手段のひとつと捉える企業も増えてきており、以前に比べ積極的に活用されるようになってきました。M&Aによる売却で大手資本企業の傘下に入ると、自社株式の現金化や代表連帯保証の解除、従業員の雇用維持などが期待できるほか、事業拡大も狙えるため、M&Aにはポジティブなイメージが浸透しつつある状況です。
買収側
M&Aの増加した背景を買収側の立場からみると、法改正や金利のマイナス化などの外的要因も少なからず影響していることがわかります。
- 法改正
買収側がM&Aを積極的に用いる要因の1つに、法改正による後押しがあります。これまで法律・税務上で曖昧に判断されていた部分が法整備されたことで、M&Aを実施しやすい環境が整いました。
- ITの発達・金利のマイナス化
また、IT技術の発達により、スピーディーに環境が変化するようになったことも要因の1つです。こうした状況下で、ゼロから新規事業を立ち上げるのではなく、M&Aにより他社のノウハウ・技術などの買収を狙う経営者が増えています。
さらに上場企業・未上場企業を問わず実質、無借金企業が増加しているため、金利がマイナス化している状況です。金融機関ではM&Aに必要な資金の貸出を積極的に行っているため、M&A実施に対するハードルが低くなったことも要因の1つといえます。
M&A業界の動向を知りたい方は下記の記事で詳しく説明しています。ぜひご一読ください。
14. これからのM&A市場
①生産年齢人口減少によるM&A増加
現在のM&A市場の規模が増大傾向にありますが、この背景には日本の少子高齢化がもたらした経営者の高齢化と後継者不足の問題が深く関係しています。
上記データのとおり、日本では生産年齢人口(15~64歳)が年々減少しています。これは、日本全体で深刻化している問題です。生産年齢人口の減少は、さまざまな業界で人手不足が生じる最大の要因と捉えられています。
特に中小企業における人材不足は経営難に直結する問題となりやすく、今後も引き続き第三者への事業承継件数が増加していく見込みです。
②業界寡占化によるM&A増加
業界寡占化によるM&A増加も予想されています。多くの企業では効率的に成長を遂げるべく、競合企業との関係性を見直している状況です。いかなる業界においても企業数が多い場合には、再編が円滑に進まず苦戦します。
例えば、メガバンク・ビール製造・新聞社・コンビニ業界などは約4社の大手企業に集約されており、競合との関係性を安定させている状況です。いかなる業界でもM&Aを用いた再編・寡占化は活用できる手段であり、企業の成長だけではなく経済の安定化も図れます。
実際に、調剤薬局業界では大手企業がシェア拡大を図るべくM&Aを積極的に活用しており、M&A実施件数が大きく伸びました。もともと調剤薬局業界ではトップ企業であっても市場シェア率が低く、シェア拡大を狙える余地が存分にあったのです。
上記の流れは調剤薬局業界だけでなく、寡占化が進む業界に広がっていくものと見られます。
③ベンチャー企業によるM&A増加
リーマン・ショック以降、低迷していた新規株式公開(IPO:Initial Public Offering)の動向も徐々に回復しつつある一方で、日本のベンチャー企業がEXITの手段としてM&Aを活用するケースが増加中です。
もともと米国ではベンチャー投資先としてM&Aが用いられてきましたが、日本でもベンチャー企業育成のためにEXIT方法のオプションとしてM&Aは重要視されています。
かつて国内スタートアップのEXITはIPOが中心でしたが、最近では差が急激に縮まっている状況です。2016年におけるIPO件数はM&A件数の約4倍でしたが、2018年において約1.4倍にまで差を縮めており、M&Aの勢いが年々盛んになっていることがわかります。
また、2019年において日本企業が関わったM&Aの件数は4,088件(前年比6.2%増)であり、3年連続で更新を続けている状況です。そして全体の約3割超は、ベンチャー企業を対象とするM&Aでした。
一般的な企業価値算定額をはるかに上回るM&A事例もあり、今後は国内企業においてもEXITの手段としてM&Aが広く活用されていくと見られます。
M&A支援機関の登録制度の創設
上記のようなM&A増加背景がある中、中小企業が安心してM&Aを進められるようにするため、M&A支援機関の登録制度が創設されることになりました。 2021年8月2日、経済産業省が登録制度の概要を発表しましたので、その概要を説明します。
制度の概要
一定の条件を満たしたM&A支援機関のみが、登録できる仕組みになります。 事業承継・引き継ぎ補助金(専門家活用型)において、登録しているM&A支援機関を利用している場合のみ、補助金の対象となります。
また登録している支援機関との間でトラブルが発生した場合、中小企業が情報提供をする窓口が創設されます。
登録条件
M&Aを支援する団体はたくさんありますが、その中でもファイナンシャルアドバイザーとM&A仲介業者のみが今回の制度の対象となります。
また、ファイナンシャルアドバイザー業務やM&A仲介業務をやっている金融機関なども対象です。 「中小M&Aガイドラインの遵守を宣言すること」が登録要件となっているため、登録されているM&A仲介会社は中小M&Aガイドラインを守っているということになります。
中小M&Aガイドラインには、仲介会社が情報の非対称性を利用して不当な取引を進めたり、M&A仲介会社を利用する人が不利になったりしないような趣旨の内容が定められているため、それを遵守している登録企業は安心して利用できるでしょう。
参考:中小企業庁「 M&A支援機関登録制度」
15. 日本の国内企業におけるM&Aの課題点
かつての国内におけるM&Aを振り返ると、敵対的買収やそれに伴う議決権の獲得合戦などが大きく話題になったこともあり、M&A自体にそれほど良いイメージがありませんでした。
しかし、近年ではM&A仲介会社やアドバイザーが増加したことを受けて、M&Aが持つ本来の定義が広く認知されるようになり「M&Aは経営戦略の1つ」というイメージが確立されつつあります。
ただし、国内のM&A市場は急成長していますが、国内企業におけるM&Aでは課題点も浮き彫りになってきている状況です。日本の国内企業におけるM&Aの課題点としては、以下の3つが挙げられます。
①M&Aに長けた人材が不足している
国内企業の動向を見ると、ITベンチャーや新たな技術・サービスの創出を目指す企業が増加傾向にあります。特に大手企業のスタートアップ企業への投資が盛んに行われています。
しかし、買い手である企業においては、投資した企業が開発した技術・ノウハウを自社の既存事業と組み合わせてシナジー効果の獲得可能性を見いだしたうえで、M&A実施を決断できる人材の不足が指摘されている状況です。
上記の要因としては、日本の大手企業のマネジメント層は新卒一括採用で雇用されており、ジェネラリストとしてキャリアを積んだ人材が大半となったことで、M&Aに長ける人材が育ちにくい環境となっている点が挙げられます。
②日本独自の人事制度
終身雇用制度の定義が事実上崩壊しかけている日本の大手企業では、年功序列を前提とした職能給が見直されたことで、成果主義の職能給が浸透しつつあります。
競争優位性を生み出すために重要となるイノベーションには、包括的な人事制度・労働改革が必要です。具体的には、個人の能力を最大限に発揮できるような制度を敷く必要があります。
上記のような改変を実施できない企業は、たとえM&Aで将来性の高い技術やノウハウを獲得できたとしても、人事制度が障害となり想像以上のシナジー効果が得られない可能性が高いでしょう。
③企業文化への対応
M&Aでは、企業が保有する経営財産・人材・技術やノウハウなども譲渡・承継の対象となります。統合後は異なる企業文化を有する従業員が同じ組織内で活動するため、さまざまな衝突・問題が発生する可能性が高いでしょう。
上記のようなトラブルは企業文化が生み出す価値観・信念などの違いによって起こりますが、それだけでなく従業員の意思決定やリーダーシップのあり方・チームワークや仕事に対する取り組み方なども影響します。
したがって、M&A実施前の人事デューデリジェンス(DD)やM&A後のPMIを通して、経営者を含む従業員全ての意識改革が求められるのです。
16. M&A用語集
M&Aの実務や、それにかかわる法律や制度などでは、専門用語がでてくる場面も多いです。この章では主なM&A用語について概要を説明します。
インカムゲイン
インカムゲインとは、不動産・株式・債券などの資産を保有している間、継続して得られる収益のことです。インカムゲインに該当するものには、不動産の賃貸収入や株式の配当金、債券利息などがあります。
エグゼキューション
エグゼキュージョンとは、M&Aプロセスにおける必要手続きの実行および管理を行うことです。M&Aの当事会社が候補先企業を決定した後の手続きや業務が該当し、使用スキームの選定・バリュエーション(企業価値評価)・交渉サポート・契約書作成・各種デューデリジェンスのサポートなどが含まれます。
エスクロー
エスクローは「第三者寄託」という意味で、M&Aの最終契約を交わした当事者間に第三者の金融機関が入って譲渡金額を決済することです。
譲渡価額の決済における安全性の確保を目的とした仲介サービスであり、エクスローを利用した場合は譲渡側・譲受側が同意した金融機関へ譲渡代金の一部を一定期間預け、契約で取り決めた条件達成時に譲渡側へ代金が支払れます。
エクスローは、アーンアウト条項が取り決められたM&Aで活用されるケースが多く、リスクを分散・軽減できる点が大きなメリットです。
オーガニックグロース
オーガニックグロースとは、自社が保有する経営資源を活かして既存事業(製品やサービスなど)の売上増加や成長を目指すことです。
既存事業を活かして自立的な成長を目指すオーガニックグロースに対し、M&Aで新規事業やサービスを取得して収益拡大あるいは成長を目指すことをM&Aグロースといいます。
オリジネーション
オリジネーションとは、M&A案件の発掘や調査・提案などを行う活動領域のことです。一般的には、M&Aのマッチングに関わる業務全般を指します。
オリジネーションは最適なマッチングのために不可欠な業務です。また、オリジネーション後のM&A手続きをエグゼキューションと呼びます。
合併比率
合併比率とは、合併における消滅会社の株式1株に対する、存続会社あるいは新設会社の株式交付割合です。存続会社・消滅会社双方の資産・負債状況や収益力、ブランド力などを考慮して決定されます。
たとえば、A社が存続会社でB社が消滅会社となる合併で合併比率が1:0.5である場合は、B社株式100株に対してA社株式は50株が交付されるかたちです。また、対等合併と呼ばれる合併では、合併比率が1対1となります。
株主間契約
株主間契約は株主間協定とも呼ばれ、特定会社の株主同士が事業運営の方法などについて締結する契約のことです。M&Aの場合、第三者割当増資や株式譲渡が行われて、複数の限定株主によって企業運営がなされるケースで株主間契約が交わされることがあります。
なお、株主間契約の効力は契約を取り交わした当事者間のみに発揮され、そのほかの株主への効力はありません。
株式の持ち合い
株式の持ち合いとは、企業同士が互いに各々の発行済株式を保有し合う状態のことです。株式を持ち合う企業同士は友好的な関係にあり、敵対的買収の防止や企業間の取引関係強化、経営権の取得などを主な目的として行われます。
株式保有特定会社
株式保有特定会社とは、保有資産のうち株式等の割合(相続税評価額による算出合計額)が50%以上の会社です。ここでいう「株式等」に該当するものには株式以外に出資と新株予約権付社債とがあり、相続税評価額によって割合(合計額)を求めます。
株式保有特定会社となるケースの多くは持株会社を作る場合であり、これは持株会社がグループ内の株式を一括保有・管理する特性上、株の保有率が必然的に上がるためです。
キャピタルゲイン
キャピタルゲインとは、企業の保有資産(株式・債権・不動産など)売却したことで得られる利益のことです。また、売却で損失がでた場合はキャピタルロスと呼びます。
焦土作戦
焦土作戦は、敵対的買収に対する防衛策のひとつです。焦土作戦では、買収側の意欲を削ぐために自社の高収益事業・資産・子会社などを意図的に売却して、自社の魅力を低下させます。ですが、株主からの反発や経営悪化のおそれがあるなどリスクの大きな方法です。
ショートリスト
ショートリストとは、M&Aマッチング時に作成したロングリストのなかから数社程度に絞り込んだリストのことです。
一般的にロングリストからショートリストへ絞り込む際は、事業内容・財務状況・地域シェア・ブランド力・ノウハウや技術などを基準にし、そのなかからM&Aの交渉相手を決定します。
スクイーズアウト
スクイーズアウトとは、企業が少数株主から強制的に株式を買い取ることです。M&Aや上場廃止実施時や迅速な意志決定が必要な場合など、大株主と少数株主の意見が対立したケースでスクイーズアウトが活用されます。また、スクイーズアウトは、2/3以上の議決権を保有していれば行うことが可能です。
スタンドスティル条項
スタンドスティル条項とは、譲渡企業から情報開示を受けた譲受候補企業が譲渡企業の同意を得ずに、委任状の勧誘や株式買い取り行為を行うことなどを一定期間禁ずる取り決めです。
スタンドスティル条項は、上場企業同士が行うM&Aでの秘密保持契約時に取り決めるケースが多く、この条項を規定することにより、敵対的買収を仕掛けるなど他社を出し抜く行為を防ぐことができます。
選択と集中
選択と集中とは、複数事業を行う企業が次式事業やコア事業、あるいは今後注力したい事業に経営資源を集中させる戦略のことです。
M&Aを行う目的となるケースも多く、選択と集中にはコスト削減や自社の強みを活かした事業価値最大化などのメリットがあります。
独占交渉権
独占交渉権とは、譲渡企業がM&A交渉中の譲受企業候補以外の第三者(法人あるいは個人)と交渉することを一定期間禁ずる権利のことです。
基本合意書において規定する権利であり、譲受候補は独占交渉権を得てからデューデリジェンスを行いM&A実行の可否を判断します。なお、独占交渉権を基本合意書で規定する場合、万一の義務違反に備え法的拘束力を持たせるケースが一般的です。
特定事業承継税制
事業承継税制とは、企業あるいは個人の事業承継時に一定要件を満たす場合は相続税や贈与税の納税猶予が受けられる制度です。税制優遇を受けた後さらに一定要件を満たせば、猶予された分の納税が免除されます。
特定事業承継税制は、2018年の税制改正によって設けられた10年間の時限措置です。従来の事業承継税制(一般措置)では一定要件を満たした事業承継の場合は相続税が80%、贈与税100%の納税が猶予されます(ただし発行済株式総数2/3まで)。
一方で、特定事業承継税制(特例措置)では発行済の全株式で猶予対象となり、相続税・贈与税とも100%納税猶予を受けることが可能です。
特定目的会社(TMK)
特定目的会社(TMK)は不動産の流動化を目的に設立した会社で、略称のTMKは特定目的会社のローマ字表記の頭文字をとったものです。
特定目的会社(TMK)は、SPC法(資産の流動化に関する法律)に基づいて設立されます。また、特定目的会社(TMK)には従業員は存在せず、資産流動化計画で定めたことのみを業務範囲とする特殊な法人形態です。
のれん
のれんは営業権とも呼ばれ、M&Aでは企業が有するノウハウ・技術力・ブランド力・取引先等との関係など無形固定資産の総称です。
一般的に、M&Aの買収価額は譲渡企業の純資産額にのれんが加わった額といわれています。
つまり、譲渡企業における将来の超過収益力を表す時価純資産から、実際のM&Aで支払った買収価額の差がのれんということです。
また、純資産よりも高値で買収された場合は「正ののれん」といい、純資産額を下回る額で買収が成立した場合は「負ののれん」と呼びます。
ノンコア事業
ノンコア事業とは、複数事業を展開する企業の中核事業(コア事業)以外の事業すべてを指し、非中核事業と呼ばれることもあります。
コア事業と比べると、割かれるリソースが少なかったり収益性が低かったりするケースが多いですが、採算がとれているかどうかが必ずしも判断基準となるわけではありません。
ノンネーム
ノンネームとは、M&A交渉の打診時に候補先企業へ提出する資料であり、譲渡企業の社名は伏せて業種・地域・大まかな事業内容などを要約した概要書です。
用紙1枚程度にまとめるため「一枚もの」とも呼ばれ、ノンネームによって候補先企業がM&A交渉を進める意思がある場合は、双方で秘密保持契約を締結してから詳細情報を開示(ネームクリア)します。
負債比率
負債比率とは財務分析指標のひとつであり、自己資本における負債割合のことです。負債比率が100%を下回っている場合は自己資本で負債を返済することができ、比率が低いほど財務の安定性が高いと判断することができます。
一般的に負債比率は100~150%が目安といわれますが、業種によっても判断基準が異なり、小売業や飲食業などは200%を超えることも多いです。
表明保証
表明保証とは、M&Aの最終契約締結日や譲渡実行日(クロージング実行日)などにおいて、譲渡企業あるいは事業の法務・財務・事業内容などの一定事項が真実かつ正確であると示したうえで当該内容を保証することです。
M&Aの表明保証は譲渡企業が譲受企業に対して行うものであり、最終契約締結時に譲受企業へ提出します。表明保証を行う内容は、たとえば開示した財務情報が正確であること・把握していない訴訟提起や偶発債務がないことなどです。
なお、表明保証の内容に虚偽があった場合、譲受企業は表明保証違反として譲渡企業へ損害賠償請求を行うことができます。
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローとは、企業が事業活動で得た利益から必要資本(運転資金や設備投資など)を差し引いた額を指し、企業が自由に使える現金のことです。
企業が事業を維持拡大するためには、継続的にフリーキャッシュフローを得ることが不可欠であり、フリーキャッシュフローの値がプラスであるほど企業の安定度は高いと判断することができます。
プロラタ方式
プロラタ方式とは、複数の金融機関から融資を受けている企業が融資額(借入額)の残高に応じて返済額を比例的に決定する方法です。
融資を受けてる企業の返済能力に変化があった場合は返済計画の見直し(リスケジュール)が行われますが、その際に融資元の金融機関に不公平が生じさせないためにプロラタ方式が採用されます。
また、プロラタ方式の返済方法は、借入残高に比例して返済額を決める「残高プロラタ」と無担保部分の借入残高に比例して返済額を決める「信用プロラタ」の2種類です。
ホワイトナイト
ホワイトナイトとは、敵対的な買収を仕掛けられた企業が防衛策として自社と友好関係にある企業に買収あるいは合併してもらう方法です。
買収防衛策のひとつであり、友好関係にある買収側企業を「ホワイトナイト」と呼びます。買収防衛策は事前準備が必要なものが多いなかホワイトナイトは不要であり、実際に敵対的買収を仕掛けられた後でも実行が可能です。
マンデート
マンデートとは「委任権限」「委任状」といった意味を持つ英語で、M&Aの場合は仲介会社あるいはアドバイザリー会社がM&A当時会社から受ける仲介依頼書(業務委任状)のことです。
一般的にマンデートという場合は、企業が金融機関から資金調達を行うときの業務委任を指しますが、M&A業界ではクロージングまでの業務に関する依頼書をいいます。
優先交渉権
優先交渉権とは、M&Aで譲受候補先企業が複数いる場合に特定の候補企業が最初に交渉できる権利のことです。
あくまでも優先交渉権がない候補先企業より先に交渉できる権利であり、独占交渉権と違って複数社に優先交渉権が付与されるケースもあります。また、優先交渉権を付与された企業が複数社となった場合、譲受候補企業の優劣はありません。
レバレッジドバイアウト
レバレッジドバイアウトとは、M&A対象企業(譲渡側)の保有資産や将来の予測キャッシュフローを担保に融資を受けて買収を行う方法です。
英語表記の頭文字をとってLBOと呼ばれることが多く、手元資金が少ない場合でも買収を実行することができます。その一方、M&A後の事業運営がうまくいかなければ融資の返済が滞るリスクも持ち合わせた方法です。
ロックアップ
M&Aのロックアップとは、譲渡対象企業(事業)の経営陣やキーマンがM&A後の一定期間において事業運営に参画することを取り決めたものです。
キーマン条項とも呼ばれ、M&A後に事業運営が困難になるリスクを軽減することができるため、多くのM&Aで最終契約書に盛り込まれます。
その一方で、譲渡企業のロックアップ対象者はM&A後の一定期間、事業運営に携わらなければならない強い制約となるものです。
ロングリスト
ロングリストとは、M&Aが成立する可能性のある候補先企業を一覧化した資料のことです。マッチング初期段階で使用され、ロングリストを基に依頼者(譲渡企業または譲受企業)は交渉を打診する企業の選定・絞り込みを行います。
M&Aのシナジー発揮が見込める企業をリストアップしたものであり、このなかから数社に絞り込んだものがショートリストです。
ADR
ADRとは、民事上の紛争解決を目指す当事者のために、専門家が公正かつ中立の立場で間に入り解決を図る手続きを行うことです。英語のAlternative Dispute Resolutionから頭文字をとったもので、日本語では裁判外紛争解決手続と呼ばれます。
ADRには司法型・民間型・行政型の3形態があり、そのなかに含まれる事業再生ADRは債務超過を抱える企業の事業再生を支援する制度です。
事業再生ADRでは、債権者と債務者の間に専門家が入り、中立の立場から金額や返済期間などの調整を行い、つなぎ融資の円滑化や税負担の軽減を図り、事業再生の早期実現を目指します。
EBITDA
EBITDAとは、企業(事業)が得た税引き前利益から利息・税金・減価償却費用および償却費用を除いたものです。
現金の出入りのみに着目して算出するため、タイミングや設備投資額の大きさによらず「企業(事業)がどのくらい利益を上げているか」を正確に知ることができ、EBITDAの値が大きいほど利益を多く獲得しているとみることができます。
M&Aにおいては、譲渡企業が売却額価格の目安を把握したい場合や、譲受候補企業が買収価額の妥当性を判断する場合に使用される財務指標です。
EBO
EBOとは、従業員が自己資金や融資などで企業の全株式または一部を取得し、経営権を獲得するM&A手法です。また、従業員が経営陣とともに経営権取得を行うケースはMEBOと呼ばれます。
EBOは従業員の利益や企業の継続性を重視する点が特徴であり、M&A後も経営方針を変えることなく事業運営が可能です。
EPS
EPSとは、1株あたりの利益を示す指標であり、企業全体の利益と発行済み株式数を比較したものです。「1株あたり純利益」と呼ばれることもあり、M&Aでは譲受企業が譲渡企業の業績を分析する際などに用いられます。
EPSにより企業の収益力と成長性をみることができ、EPSの値が高いほど「企業の稼ぐ力」が大きく魅力的な企業(投資先)と判断することが可能です。
EVA
EVAとは、企業の経営効率を評価する指標であり、企業が実際に得た利益から、投資家が必要とした最低限の利益を引いたものです。
EVAは、企業が投資家に対して付加価値をどれだけ生み出しているかを評価するために用いられます。
CA
CAとは秘密保持契約のことであり、Confidentiality Agreementの頭文字をとったものです。また、NDA(Non-Disclosure Agreementの頭文字をとったもの)と呼ばれることもあります。
秘密保持契約は、知り得た情報(一般開示されていないもの)を取り決めた目的以外で使用しないことかつ第三者に漏洩しないことを書面にし約束するものです。
M&Aを進めていること自体が企業にとって秘密事項ともなるため、秘密保持契約の締結は非常に重要な意味を持ち、交渉前の企業概要書開示時、基本合意締結時、最終契約締結時などで秘密保持契約を締結します。
IM
IMとは、譲渡企業(あるいは事業)の詳細情報を記載した資料のことで、Information Memorundomの頭文字をとったものです。
IMに記載される情報には、譲渡企業の経営方針・業績・財務情報などが含まれており、譲受候補企業はIMの内容からM&A交渉を進めるか否かを判断します。
IRR
IRRとは、投資収益率を示す指標の一つであり、投資によって得られたキャッシュフローから初期費用や出口費用を考慮して算出される収益率です。Internal Rate of Returnの頭文字をとったもので、日本語では内部収益率と呼ばれています。
IRRでわかることは投資額に対してリターンをどの程度効率的に得られるか、年あたりの利回りがどのくらいかということです。一般的に、IRRの値が大きいほど収益性が高く投資対象として有利であると評価されます。
LBO
レバレッジドバイアウトのことを指し、英語表記の頭文字を取った略称です。
MOU
MOUとはM&Aの基本合意書のことで、Memorandum of Understandingの頭文字をとったものです。基本合意書には、その時点で合意した譲渡対象(あるいは範囲)や価額などの条件を記載します。
基本合意時点の内容を確認する意味合いで締結するため、一般的に独占交渉権や秘密保持など一部条項を除き法的拘束力はありません。
PER
PERとは、対象企業の株価が1株あたり純利益(EPS)の何倍かをみる指標で、Price Earnings Ratioの頭文字をとったものです。
日本語では株価利益倍率と呼ばれ、M&Aでは譲受候補企業が譲渡企業の株価について、割安性(もしくは割高性)を判断するために用いられます。
PERの値が大きいほど利益に比べて株価が割高であり、PERの値が小さいほど割安であると判断することが可能です。ただし、成長性の高い企業においては、PERの値が大きくなる傾向があります。
PMI
PMIとは、M&A完了後に行う統合プロセスのことであり、Post Merger Integrationの頭文字をとったものです。
M&A後の事業運営を円滑に進め、シナジーなどのM&A効果を最大化させることが目的であり、そのために意識・経営・業務の3つにかかわる全プロセスが範囲の対象となります。
PMIの成否は、M&A検討時に想定していたシナジー効果の発揮や売上拡大などの実現に影響するため、非常に重要な工程です。
TSA
TSAとは、M&A実施後の移行期間の事業サービスについて、その管理や責任所在を取り決める契約のことで、Transition Service Agreementの頭文字をとったものです。
カーブアウト(事業の一部を切り出して売却する手法)を伴うM&Aで主に締結されるものであり、一般的には最終契約と同時に締結します。
TSAは、譲渡側・譲受側がM&A実施前に行っていた事業サービスを、移行期間中どのように管理するかを決めておく場合に効果的です。
17. M&Aに関するQ&A
M&Aに関する疑問で多くみられるのは、以下の8つがあります。
①少しでも高く売却する秘訣は?
買い手とのM&A交渉において、「買収する価値のある会社」であることをアピールしていくことが大切です。
しかしながら、M&Aを開始すると、経営者にさまざまなプロセスの実施が求められるため、日常業務がおろそかになってしまいやすいでしょう。これにより自社の業績が低下してしまうと、買い手からの印象を落としかねません。
好条件での取引を目指す場合、M&Aによる売却が決定したら業績の伸長を最優先に考えましょう。そのためにも、M&Aで必要なプロセスは、仲介会社などの専門家のサポートを得ながらスムーズに進めていくことをおすすめします。
②赤字や債務超過の企業はM&Aできない?
結論から述べると、赤字・債務超過の企業であってもM&Aできる可能性は十分にあります。たとえ、それまでの経営状態が悪くても、適切に再生処理をこなしていけば、M&Aによる売却を目指せるのです。
また、そもそも赤字に関する誤解も多く見られます。具体例を挙げるならば、赤字が一時的な投資により生じている企業です。こうした企業では、投資に成功して利益が生じれば、赤字から脱却する可能性が大いにあります。
さらに、赤字会社の中に優秀な人材が眠っているケースも多いでしょう。企業が赤字の場合でも、その人材が巨額の利益を生み出す可能性は十分にあることから、M&Aにより買収を希望する企業は少なくありません。
M&Aによる売却を目指すうえで大切なポイントは、赤字・債務超過の程度や理由を明らかにしておくことだといえます。会社の状況を十分に整理しておくと、「自社であれば経営状態の改善や立て直しができる」と考える買い手が見つかる可能性が高いでしょう。
③M&Aの成約はどれくれらいの期間がかかる?
一般的に、M&Aの成立までにかかる期間は「短くても半年程度」といわれています。ですが、M&A対象となる企業(あるいは事業)の規模や業種、地域性、希望条件によっても変わるため、もっと長い期間かかるケースもあれば短期間で成立するケースもあるでしょう。
また、M&Aは必ず成立するという保証があるものではありません。希望条件に合った相手先企業がみつからなかったり、交渉が不成立になったりする可能性もあるため、半年程度かかるというのはあくまでも一般論と考えておいたほうがよいでしょう。
そして、M&Aが成立するためには実施タイミングも重要です。M&Aを検討している場合は早期から準備を進めておき、業界でのM&A動向をみながらタイミングを逃さずに行うことで、成約確立向上や短期間でのM&A成立にも期待できるようになります。
④金融機関・公的機関・士業事務所とM&A仲介会社の違いは?
M&Aに関する相談先には、仲介会社・アドバイザー以外にも以下のようなものがあります。
- 金融機関
- 公的機関(事業引継ぎ支援センター)
- 士業事務所(税理士・会計士・弁護士事務所)
ただし、上記に挙げた機関は、かならずしもM&Aに関する知識・実績・経験が豊富でないケースも多く、適切なマッチングを図れなかったり、プロセスにかかる時間が長引いたりするおそれがあります。
M&Aの成否に直接影響する場合もあるため、成功確率を高めたい場合にはM&Aで実績のある士業事務所か、M&A仲介会社・アドバイザーに相談・依頼しましょう。なお、依頼先を決める際には、複数機関に相談したうえで、M&Aの知識・実績・経験・人柄などを比べることをおすすめします。
M&Aの相談先については以下の記事で詳しくご説明していますので、そちらもご一読ください。
⑤完全成功報酬制のメリットは?
完全成功報酬制を採用する仲介会社に依頼すると、M&Aが成立しない限り手数料の支払いは一切求められません。そのため、実際にM&Aが成立するのかどうか不安に感じている場合であっても、費用面でのリスクを最小限に抑えたうえでM&Aの実施を図れるのです。
また、着手金制のM&A仲介会社では、着手金を取ることだけを目的として、クライアントに対して通常よりも高額な企業価値算定を提示する可能性があります。その結果、買い手が現れず、譲渡自体が困難になるケースも多いでしょう。
その一方で、売り手・買い手ともに着手金を無料とするM&A仲介会社に依頼すれば、着手金の存在により検討を断られることがなく、多数の買い手候補に同時並行で提案・交渉を行えます。
なお、手数料はM&A成立時に請求されるため、M&Aで獲得した譲渡益を手数料の支払いに充てることも可能です。
⑥秘密保持契約書を締結しないとどんな問題が発生するの?
M&A仲介会社・アドバイザーへの相談時に秘密保持契約書を締結しておかないと、自社が提供した資料などから機密情報が漏えいしてしまいかねません。
M&Aを検討している情報が広まれば、「経営状態が悪いのでは?」という憶測を呼び、自社の従業員・取引先などを動揺させてしまうおそれもあります。その結果、従業員が離職してしまったり、取引先から取引を打ち切られたりする可能性が考えられるのです。
上場企業の場合、外部に情報が漏れてしまえば、自社の株価に悪影響をおよぼす場合もあります。こうしたトラブルを発生させないためにも、秘密保持契約を締結しておきましょう。
⑦見せたくない書類は提供しなくてもよいの?
M&Aで提出する書類の中には自社にとって不利な情報が含まれるケースもあるかと思いますが、こうした情報も含めて隠さずに提供しましょう。
なぜなら、虚偽の申告をしたままM&Aの手続きを進めてしまうと、相手企業との間でトラブルが発生する可能性が高いためです。
基本合意後に虚偽の申告が発覚すれば、譲渡価額が著しく低下してしまったり、M&A取引そのものが破談となってしまったりするおそれがあります。必要となる情報を全て開示したうえで、自社にとって最適な相手企業を探していきましょう。
⑧従業員や取引先に対するM&Aの公表はいつ行うの?
従業員・取引先に対してM&Aを公表するタイミングは、M&Aの成立後が良いでしょう。ここでは、誠意を持ってM&A成立を報告することが大切です。
従業員・取引先を誤解させたりネガティブな印象を与えたりしないよう、あらかじめアドバイザーに相談したうえで説明方法を検討しましょう。
M&Aの公表後は、速やかに統合プロセスに移行します。従業員の引き継ぎが円滑に進むよう、経営者の方も自社に一定期間、残りながら統合プロセスを完了させてください。
⑨仲介会社に依頼せず自分でM&Aを進めてもいいの?
仲介会社が絶対に必要なわけではないので、アドバイザーを使わずに自分でM&Aを進めることも可能です。
仲介会社を利用するメリットとして「買い手候補に幅広くアプローチできること」と「交渉がスムーズに進められること」があります。
自分ひとりで進めると、まず多くの買い手候補にアプローチすることが難しくなります。
知り合いの社長などに声をかけたり、マッチングプラットフォームを利用したりする方法等はありますが、それでも仲介会社が持つネットワークを利用した方が、圧倒的にたくさんの候補先にアプローチすることが見込めます。
また、仲介会社などの専門家を利用しないと、交渉をスムーズに進めるのが困難になる場合もあります。ひとりで進めると、どのタイミングでどういう資料の準備が必要かを事前に把握することができず、時間がかかってしまいます。
また不利な条件で契約をしてしまう可能性などもあります。
自分ひとりでM&Aを進めることも可能ですが、仲介会社などの専門家に依頼をした方が不要なリスクを低減することができます。
18. まとめ
M&Aは、近年増加している後継者問題や市場縮小をはじめ、さまざまな経営課題の解決方法として活用されています。M&Aで享受できるメリットは予想を上回ることがある一方で、失敗すると企業にとって大きな損失となりかねません。
M&Aを成功させるには、細かなプロセスの定義や意味を踏まえたうえで、自社に合った戦略を策定すると良いでしょう。しかし、M&Aの検討・実施には専門的な知識や見解が必要となる場合が多く、経営陣のみで進めていくのは決して簡単ではありません。
したがって、自社に適したM&A仲介会社などの専門家を起用することがM&Aを成功させる大きなポイントとなります。
M&A・事業承継のご相談ならM&A総合研究所
M&A・事業承継のご相談なら経験豊富なM&AアドバイザーのいるM&A総合研究所にご相談ください。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。
M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴
- 譲渡企業様完全成功報酬!
- 最短49日、平均7.0ヶ月のスピード成約(2024年9月期実績)
- 上場の信頼感と豊富な実績
- 譲受企業専門部署による強いマッチング力
M&A総合研究所は、成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A仲介会社です。
M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。
また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。
相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。